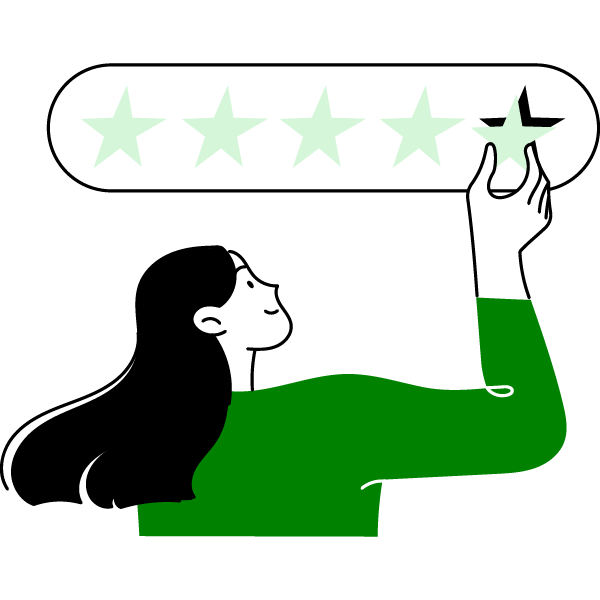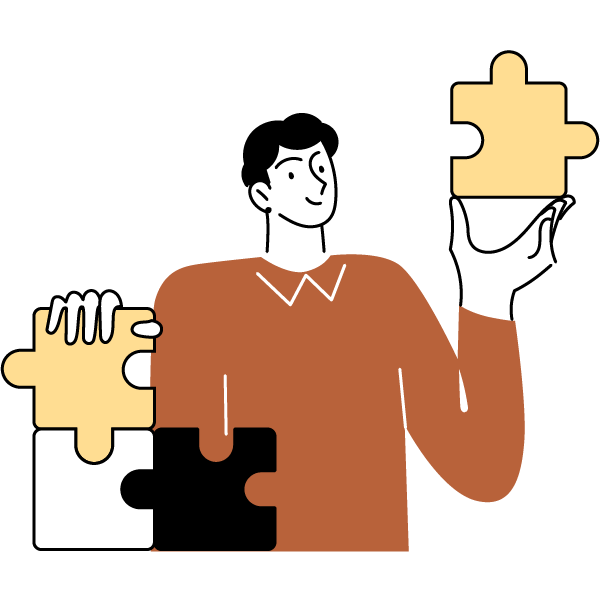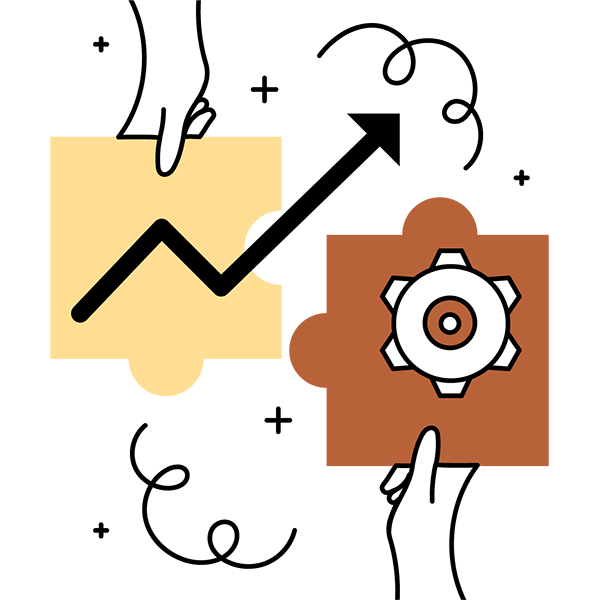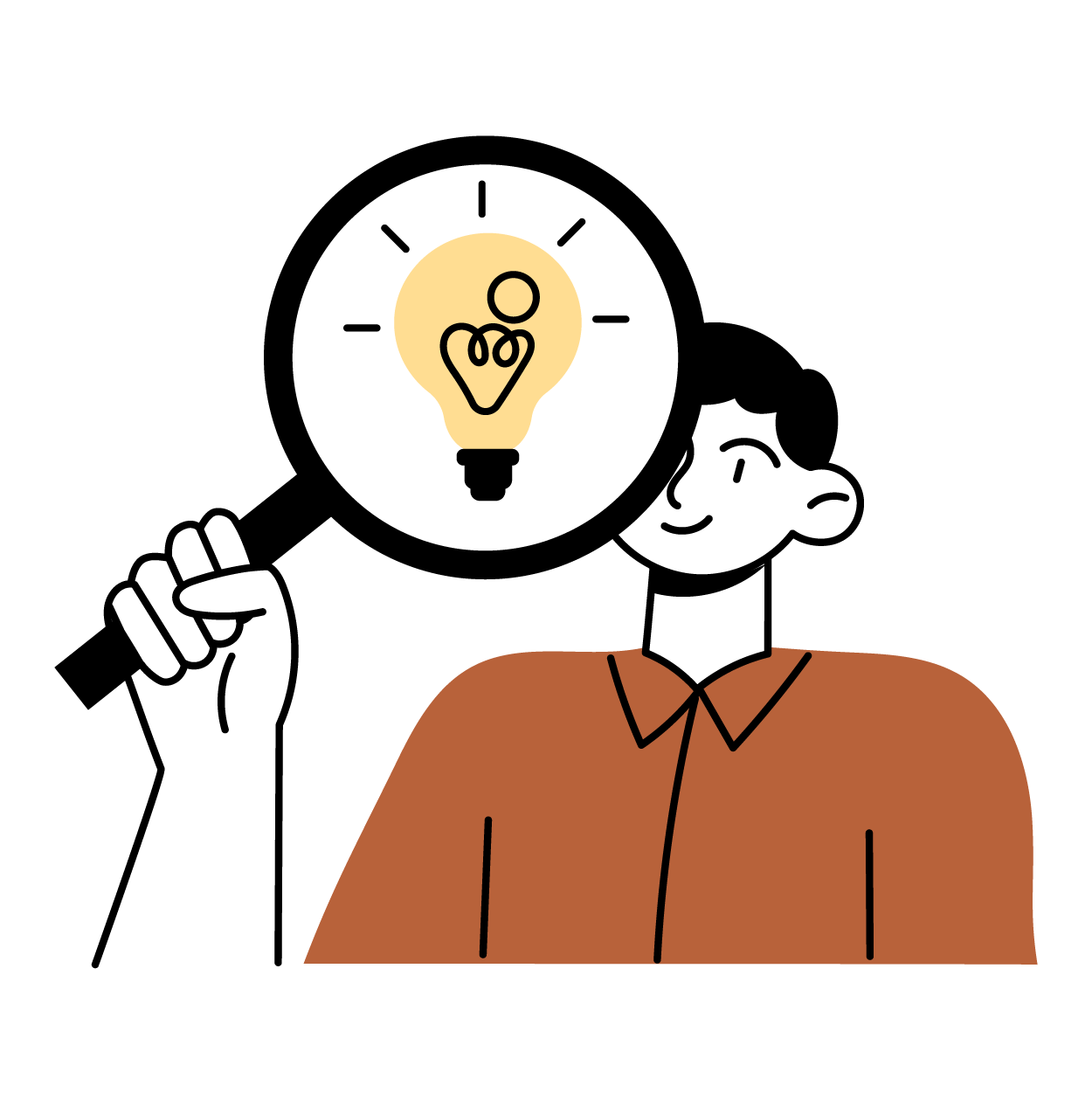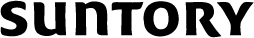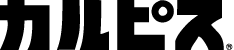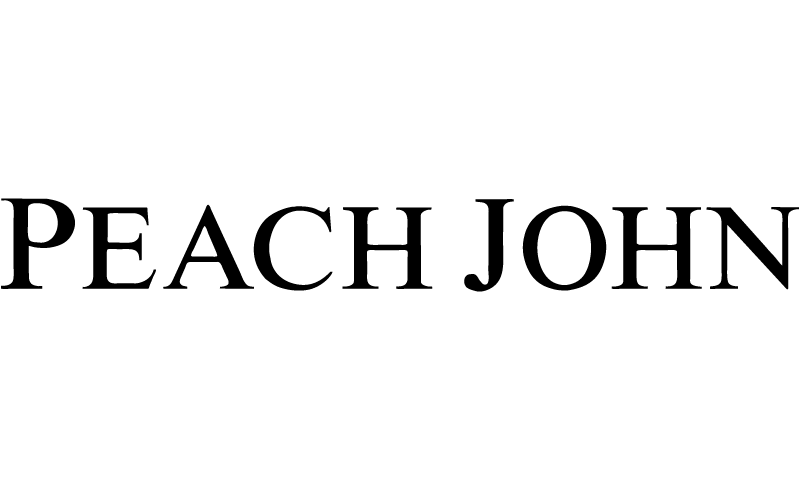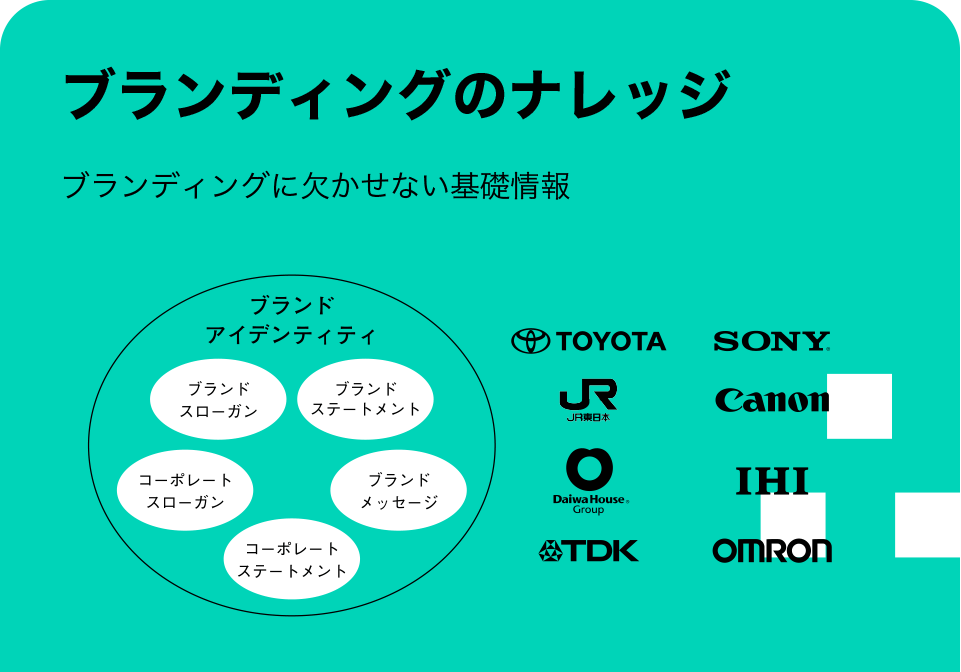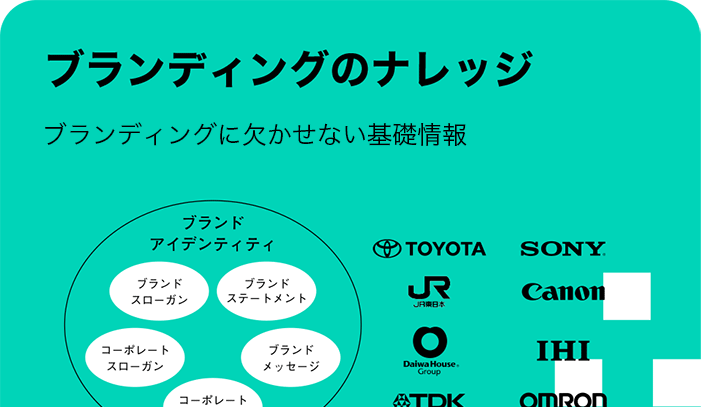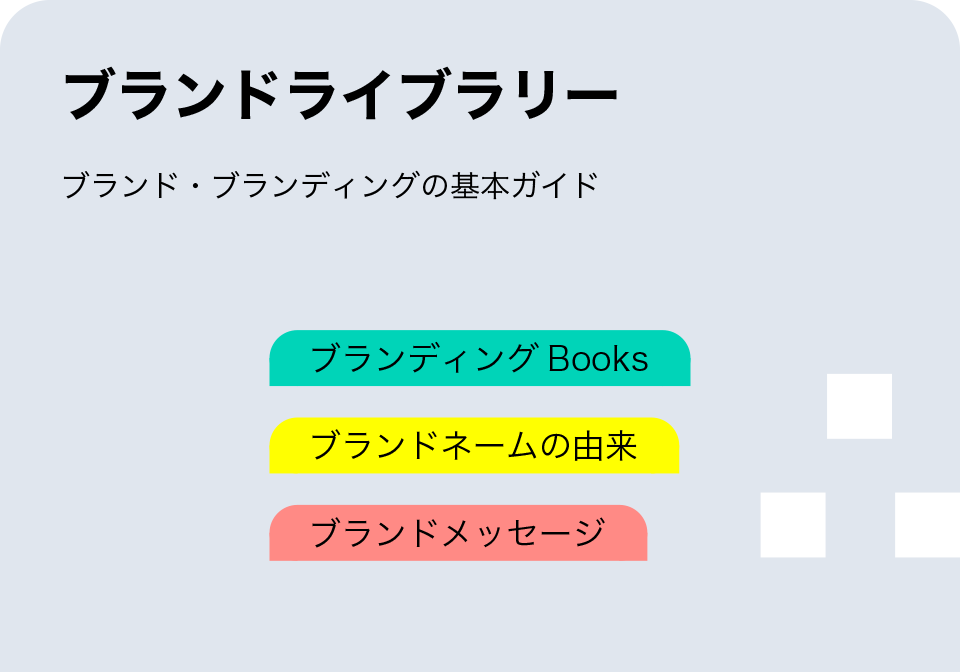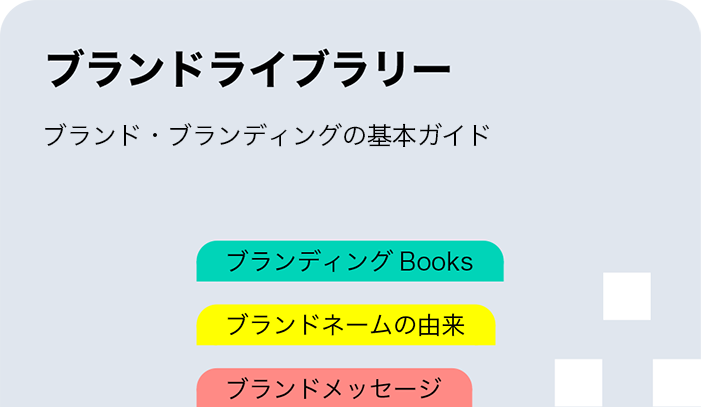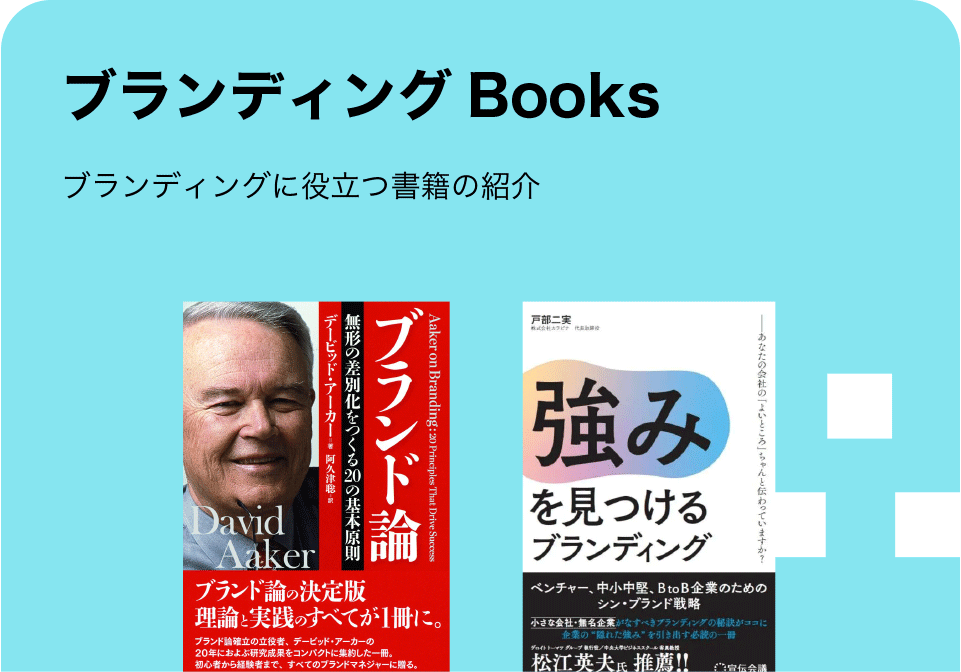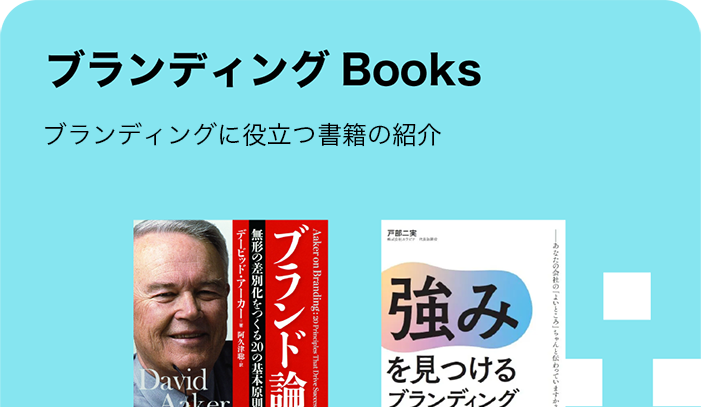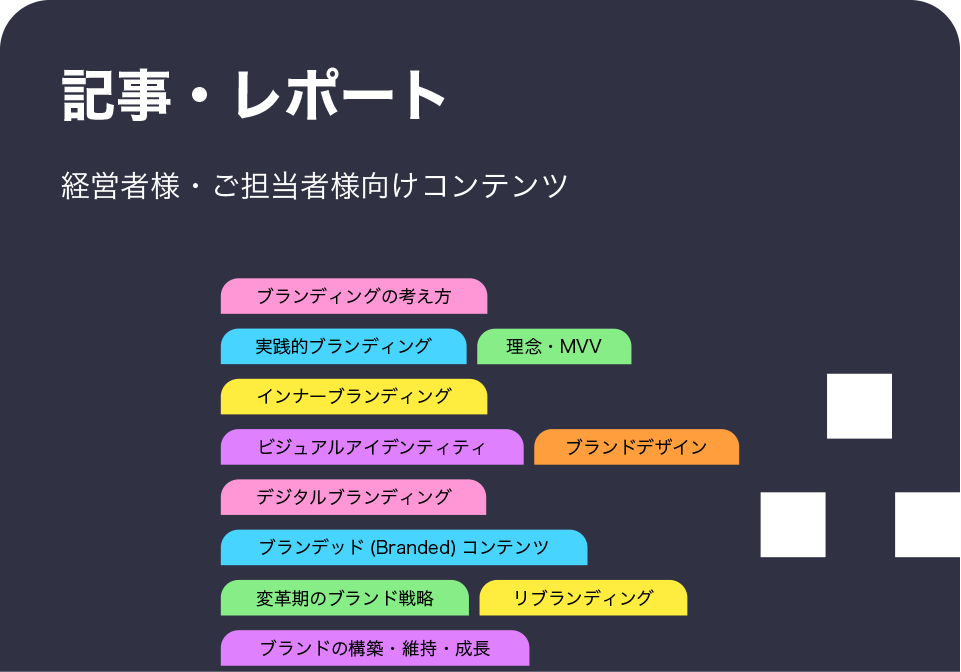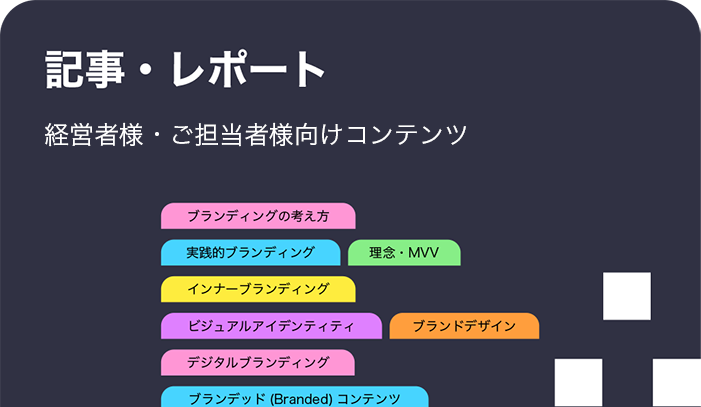リブランディング
リブランディングを成功させるには? 企業ブランド再構築の基本と注意点
2025年10月7日 11分読み

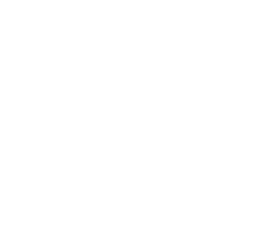
エグゼクティブサマリー
市場や顧客の価値観が急速に変化するなかで、かつてのブランド力を十分に発揮できなくなってしまう企業が増えています。ロゴを刷新したりするだけでは、企業ブランドの再生にはつながりません。求められているのは“企業ブランドの再構築”です。
企業ブランドを再構築することを意味する「リブランディング」は、単なるイメージの変更ではなく、企業の存在意義や提供価値を改めて見直し、それを組織と市場の双方に再び浸透させるプロセスを指します。そのプロセスでは、経営戦略とブランド戦略の整合性が問われ、社内外の認識を揃えることが欠かせません。
本レポートでは、「リブランディングがなぜ必要になるのか」「リブランディングの考え方と進め方」「リブランディング成功のポイント」を、実際の中小企業の成功事例を交えながら解説します。
なぜリブランディングが必要になるのか
企業ブランドは、その企業が歩んできた年月の中で形づくられます。そのため創業当初に定めた理念や価値観が、変化する市場や顧客とずれ始めることは不自然なことではありません。問題は、そのずれに気づかず、従来のブランドを惰性のまま維持してしまうことにあります。
特に中堅・中小企業では、事業の多角化や代替わり、組織の拡大などによって、社内のブランド理解が分散しやすくなります。「何を大切にしてきたのか」「自社は何者なのか」という問いに、経営陣と現場が同じ答えを持てない状態が続くと、ブランド力は確実に弱まります。
また、顧客側の変化も見逃せません。デジタル化や価値観の多様化によって、選択や購入の基準が「安い」「便利」から「共感できる」「信頼できる」へと移行しています。そうしたなかで、旧態依然としたブランドのままでは、顧客の心に届かなくなるのです。
つまりリブランディングは、企業が時代との接続を取り戻すための経営的取り組みです。見た目の刷新だけではなく、企業のアイデンティティをもう一度明確化し、未来に向けて再定義する作業に他なりません。
リブランディングの考え方と進め方
リブランディングの第一歩は、「なぜ、今、再構築が必要なのか」を明確にすることです。売上や認知度の低下といった表面的な課題の背後には、必ず“存在意義の埋没”があります。経営者がこの点を直視しないまま外見を変えても、結果は長続きしません。
1)現状分析とブランド診断
まず行うべきは、現状のブランドがどのように認識されているかを正しく把握することです。社会環境のインサイト、社内・社外インタビュー、顧客アンケート、競合比較などを通じて、
- どのような印象を持たれているか(イメージ)
- どのような価値を感じてもらえているか(価値)
- どのような共感や信頼があるか(関係)
を可視化します。
この段階では「良し悪し」を判断するのではなく、「現実」を正確に知ることが目的です。ここで浮かび上がるギャップこそ、再構築の起点になります。
2)企業ブランドの再定義
次に、企業ブランドの核となる“存在意義(Why)”を再確認します。創業時の理念に立ち返ることもあれば、現在の社会課題や顧客の変化に照らして再構築することもあります。ここでは、「何を提供している会社か」ではなく、「何のために存在している会社か」を問うことが重要です。
この問いに対する答えが、企業文化や行動指針を再整理する軸になります。企業が進むべき方向性に部門を超えて一貫性を持たせることで、社内・社外への発信がぶれない企業ブランドが形成されます。
3)体験設計と発信
ブランドは言葉だけでは浸透しません。製品やサービス、社員のふるまい、Webサイトや店舗のデザインなど、あらゆる接点が一貫した体験を生み出すことが重要です。ロゴやコピーなどのクリエイティブ要素は、ブランドの核が明確になったあとに検討するのが原則です。
発信フェーズでは、「リニューアルしました」と伝えるのではなく、ブランドが何を目指して再定義されたのか、その背景を語ることが共感につながります。
具体的な事例
事例❶ やまやコミュニケーションズ(福岡県)
福岡県を拠点に辛子明太子の製造・販売を行う食品メーカー「やまや(やまやコミュニケーションズ)」は、創業50周年を迎えた際、全国展開を進める中でブランドの認知度と一貫性に課題を抱えていました。地域色の強いブランドイメージが全国市場での浸透を妨げていたのです。そこで、「九州から世界へ、やまやスタンダードを。」という新しいビジョンのもと「Made in KYUSHU」というスローガンを策定。これにより、地域の食文化を全国に発信する姿勢を明確にし、ブランドの一貫性を高めました。

企業ブランドの再構築を通じて、やまやは地域密着型のイメージを整理し、全国展開に向けた事業基盤の整備を進めています。
事例❷ ツインバード(新潟県)
新潟県燕三条市を拠点とする家電メーカー「ツインバード」は、創業70年以上の歴史に甘んじることなく、時代の変化に対応するためブランド再構築に取り組みました。従来のコスト優位型の製品イメージを刷新するため、社内ワークショップやアンケートを通じて企業の中核価値を見直しました。その結果、高価格帯の「匠ブランジェトースター」を投入し、新たなブランド価値を市場に訴求しました。
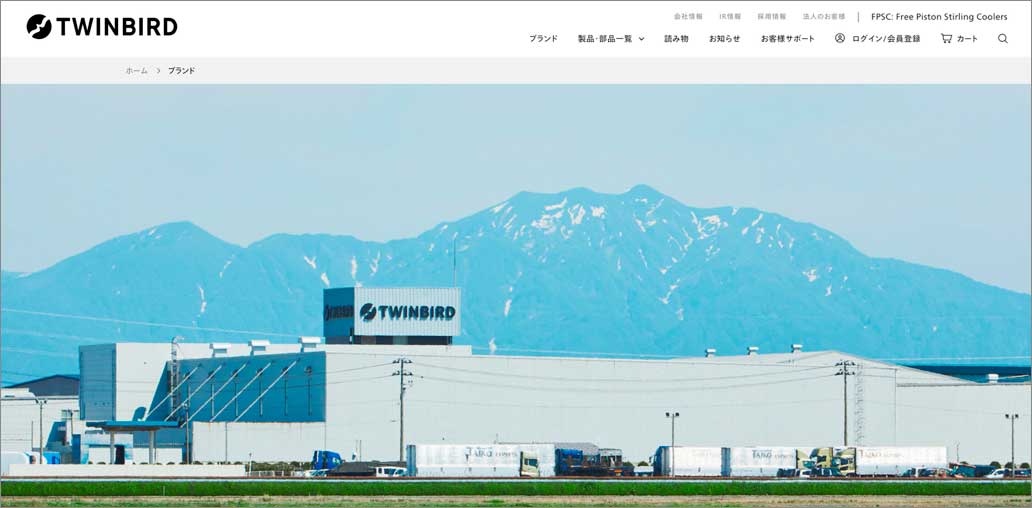
こうした取り組みの結果、2023年秋に発売した「匠ブランジェトースター」は価格が2万5,800円と高価格帯でありながら、想定の4倍の売れ行きを記録。いまツインバードブランドは、伝統を守りつつ革新を追求する新ブランドへと生まれ変わりつつあります。
事例❸ コクヨ(大阪府)
1905年創業の文房具メーカー「コクヨ」は、創業120周年を迎えるにあたり、従来のブランドイメージでは事業領域の拡張や新規事業展開の価値を十分に伝えられないという課題に直面しました。国内外での認知向上や、企業価値の一貫した発信も求められる中、企業ブランドの刷新を決断。新たなブランドメッセージ「好奇心を人生に」を策定し、ロゴを含むコーポレートアイデンティティを刷新しました。
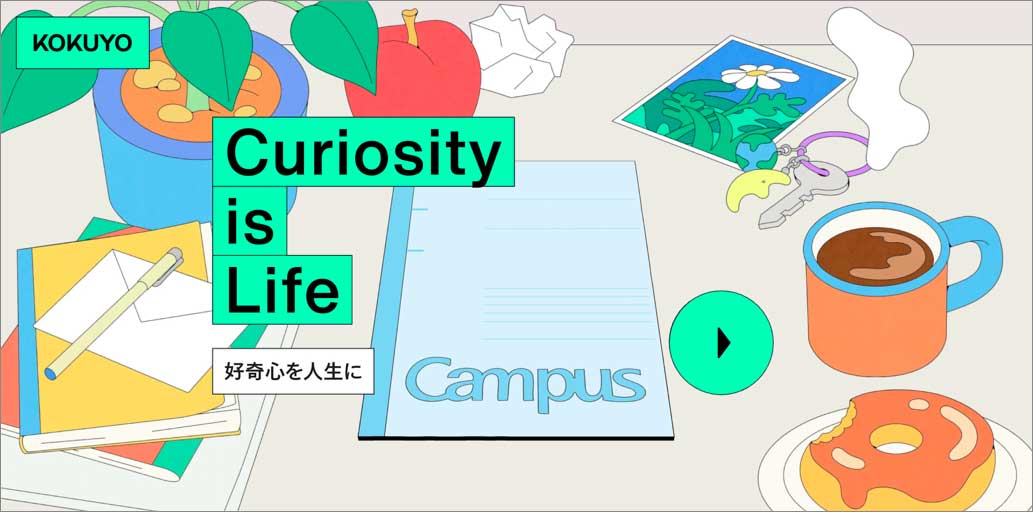
たとえばリブランディングの一環として、ブランドメッセージ「Curiosity is Life(好奇心を人生に)」をテーマにした短編映画「The Curiosity Films」を制作し、公式YouTubeなどで公開。この取り組みにより、社員や生活者に向けてコクヨが目指す価値観や事業の方向性を具体的に伝える場を創出しました。また、文具や家具にとらわれない事業領域の拡張や新たな取り組みを象徴する新たな展開として、ブランドの拡張性を実践する役割も果たしています。
リブランディング成功のポイント
1)経営主導のプロジェクトにする
企業ブランドの再構築は、経営課題そのものです。デザイン部門や広報部門に任せきりにするのではなく、経営者自身がブランドの目的と方向性を明確にし、全社員に示すことが成功の前提となります。
2)社内外の一貫性を重視する
外向きの発信だけを整えても、社員がブランドの意義を理解していなければ効果は持続しません。社内浸透と外部発信を並行して行い、「語るブランド」から「体現するブランド」へと進化させることが重要です。
3)短期成果ではなく、中長期視点で捉える
企業ブランドの再構築は、短期的な施策ではなく、企業の価値基盤を再整備する長期的な取り組みです。効果を「売上」だけで測るのではなく、「社員の共通理解」「顧客からの信頼」「採用市場での認知」など、多面的に評価することが求められます。
まとめ
リブランディング(企業ブランドの再構築)は、過去を否定する行為ではありません。むしろ、これまで積み重ねてきた価値を新しい時代にどう生かすかを明確にする取り組みです。
中堅・中小企業にとって、リブランディングは「大企業の話」ではなく、自社の成長を左右する現実的なテーマです。変化の激しい時代にこそ、企業は「自分たちは何者か」「何を約束するのか」を再び見つめ直す必要があるでしょう。その問いへの答えこそが、次の時代に選ばれる企業ブランドをつくる原動力になるのです。
支えるブランド推進室
最新レポート
関連レポート
ブランドライブラリー
ブランドライブラリーの
最新情報

そのブランドに、
次の一手を。
「まだ依頼するか決めていない」段階でも、
多くの相談をいただいています。
-
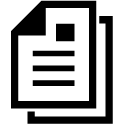
社内検討や実施
判断に活用できる
PDF資料を
ご用意しています -
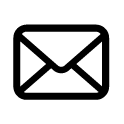
ご質問・ご相談は
フォームより
お問い合わせ
ください -
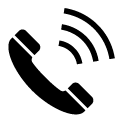
担当者が
直接ご対応します
10時〜18時
(平日)
このレポートについて
フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター
広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。
これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。