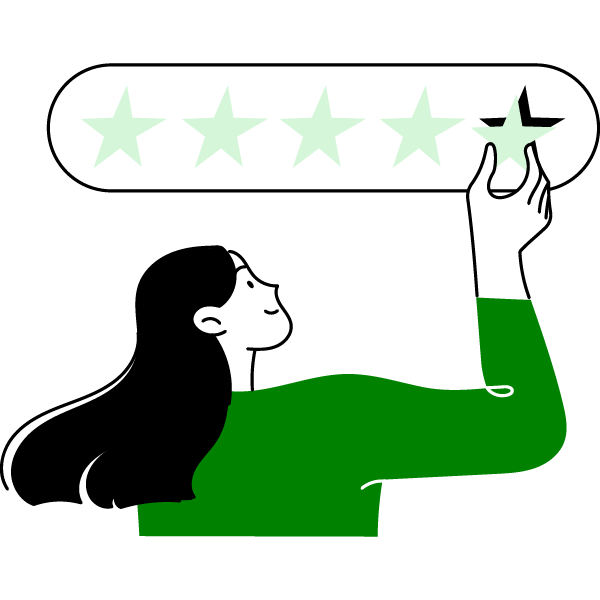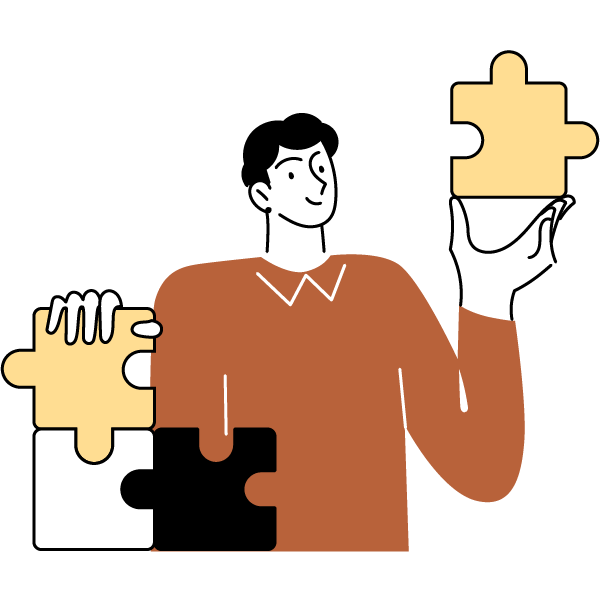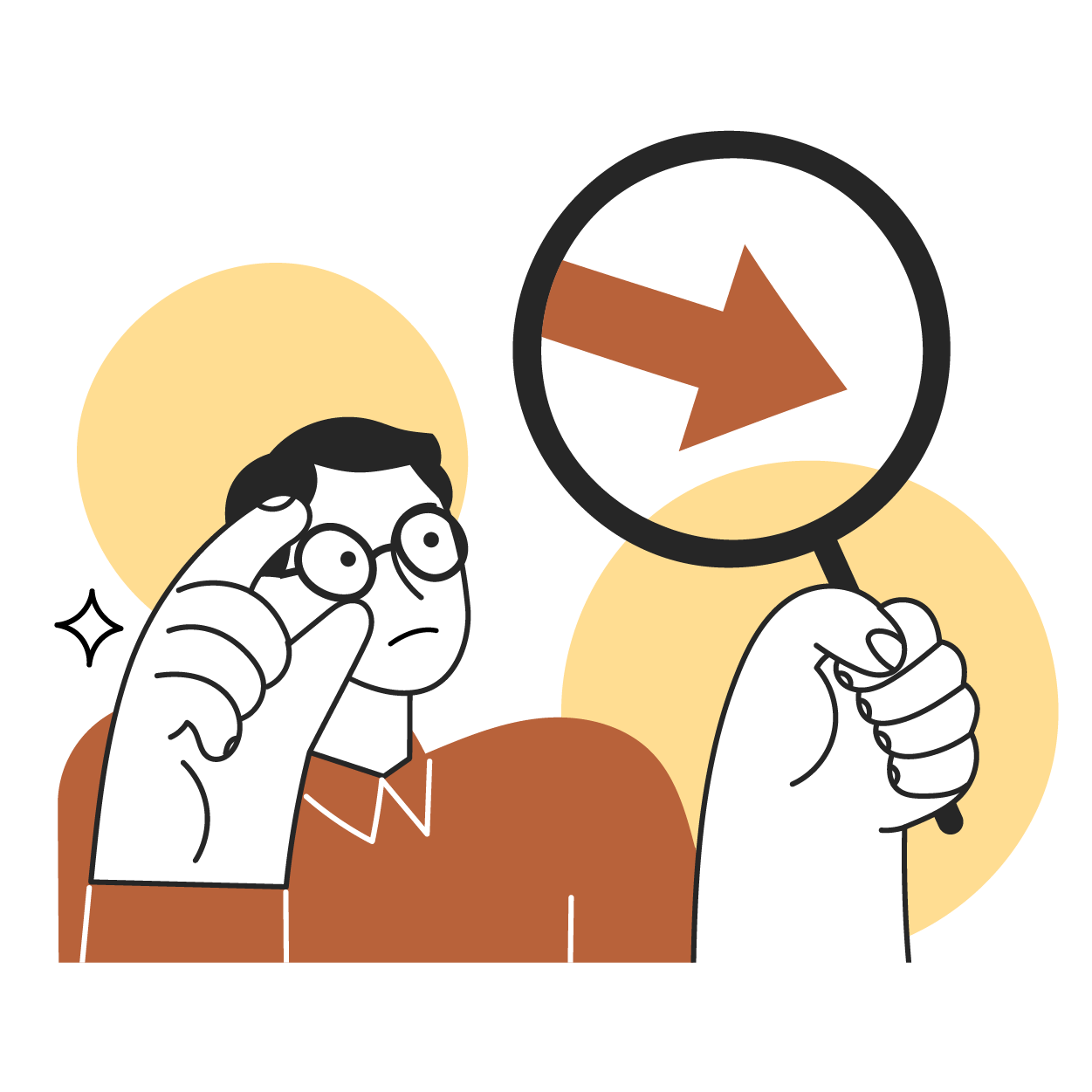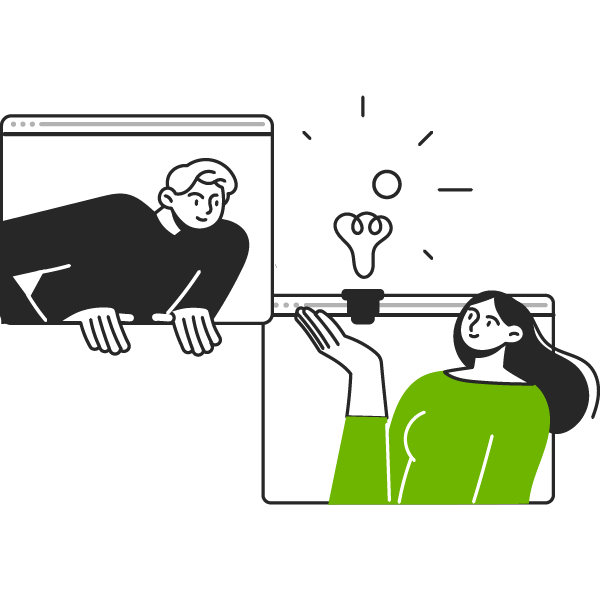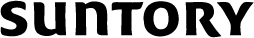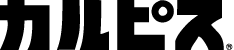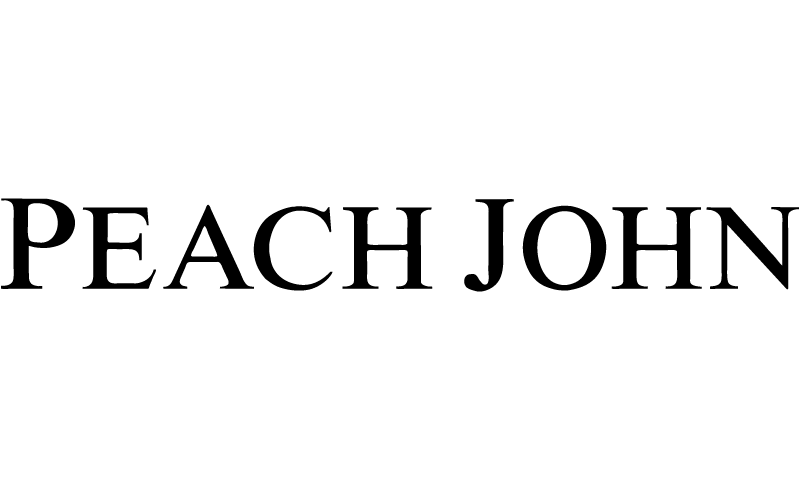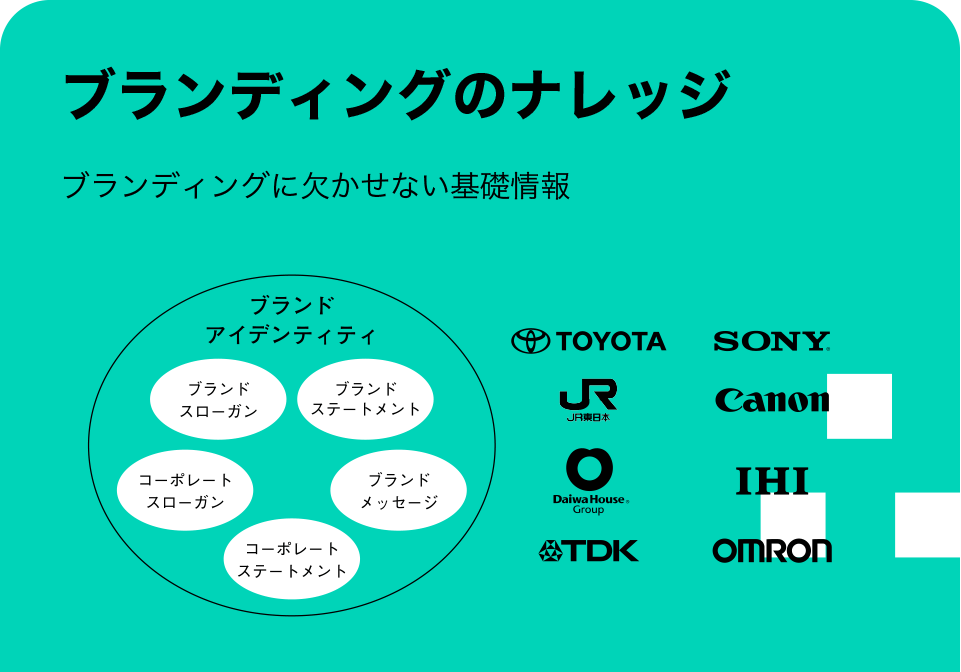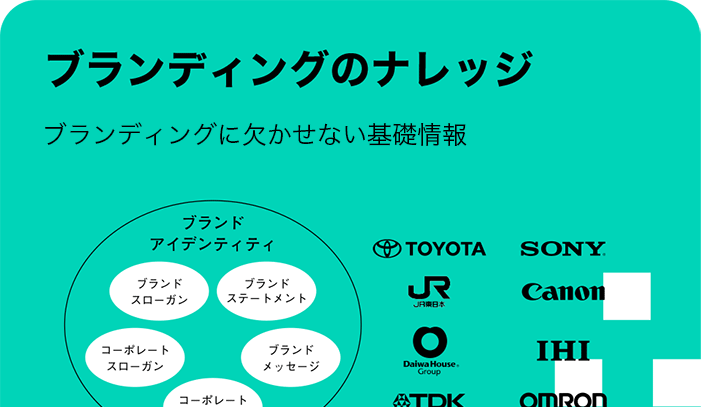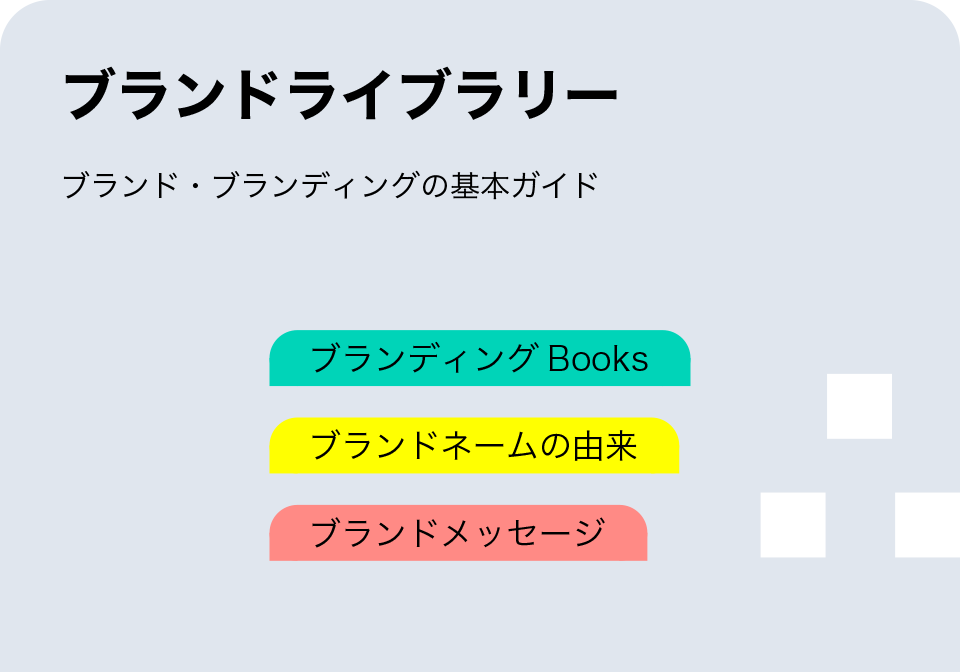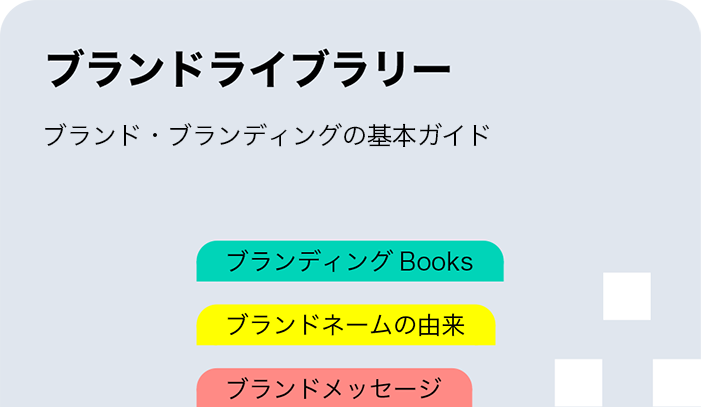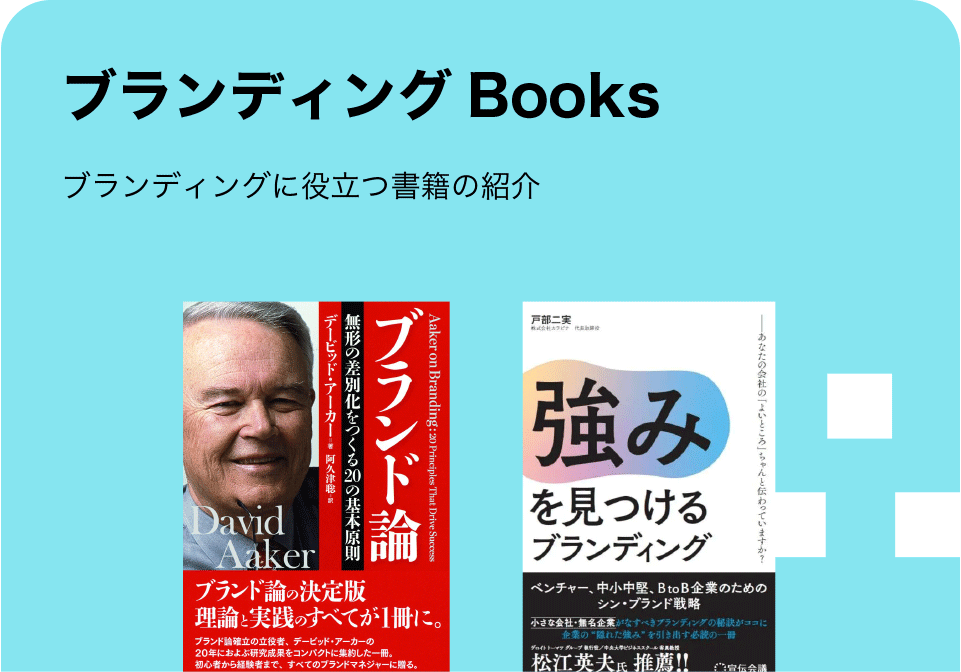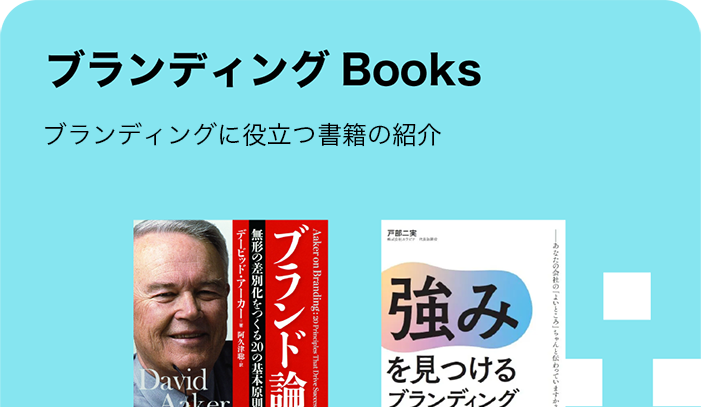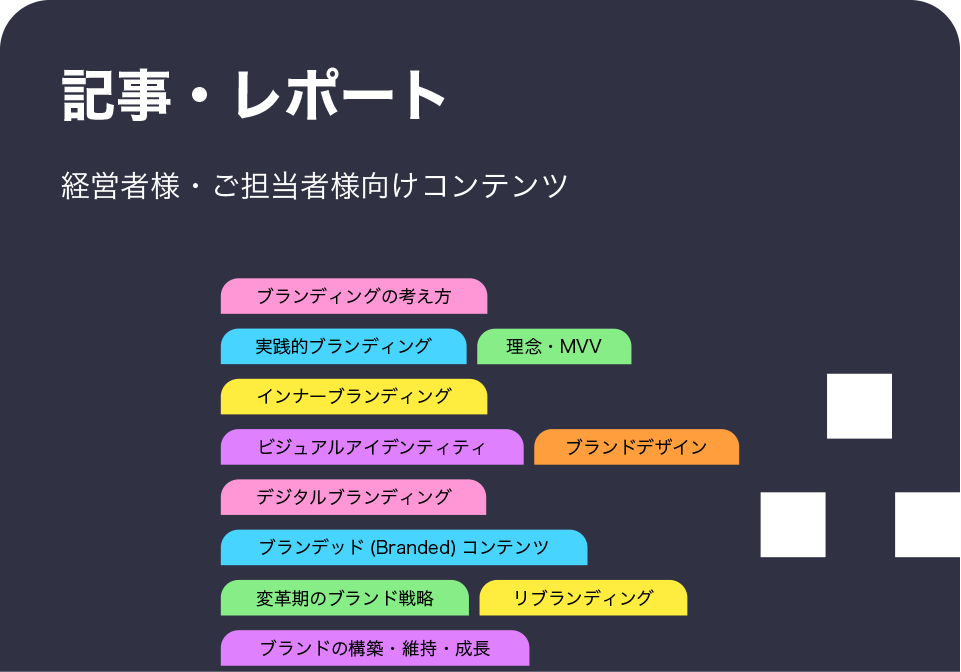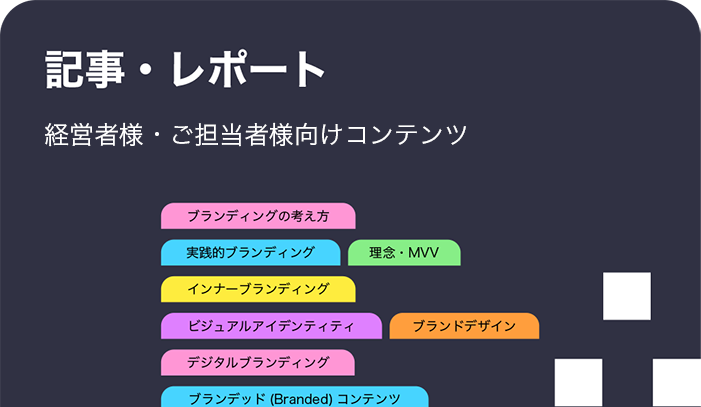理念・MVV・パーパス
経営層が知らない、社員が企業理念を理解しない理由
2025年5月3日 11分読み
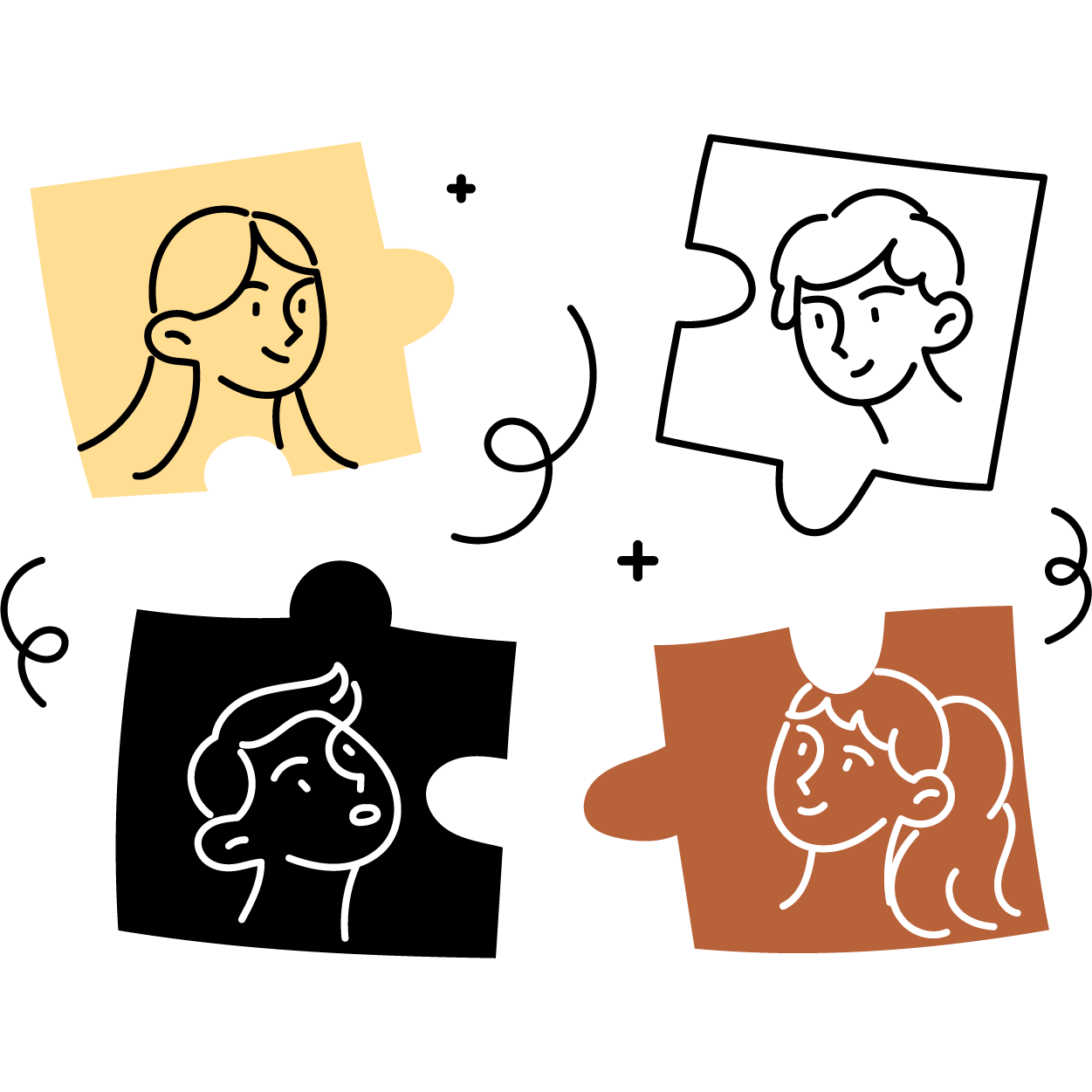
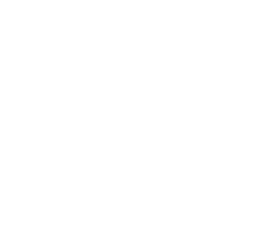
エグゼクティブサマリー
企業理念は企業の方向性を示す重要な指針であり、経営層の意思を社員に伝えるための重要なツールです。しかし、現実的には多くの企業において、社員は企業理念を理解していない、もしくは実際の業務に反映させていないという問題があります。
この問題は、経営層がどれだけ素晴らしい理念を打ち出しても、それが組織内で共有され、実践されなければ意味がありません。本レポートでは、その原因と解決策について、事例を交えながら解説します。
社員が企業理念を理解しない理由
企業理念は経営層のビジョンを反映したものであり、企業の目指す方向性を示す重要な指針です。しかし、企業理念が社員に十分に理解されていない場合、組織内でその意義が薄れてしまいます。社員が企業理念を理解しない理由は多岐にわたります。ここではその主な要因をいくつかの観点で説明します。
① 理念の抽象性
企業理念は、しばしば抽象的で理想的な表現で示されることが多いです。この抽象性が社員にとって理解しにくく、日々の業務にどう反映させればよいのかがわからない原因となります。たとえば「社会貢献」といった理念は一見素晴らしいものの、社員がそれをどう実務に活かすかは非常に曖昧です。結果として、理念の理解に差が生まれ、現場でその実現に向けた具体的な行動に繋がりません。
② コミュニケーション不足
理念を経営層がどれだけ熱心に発信しても、社員がそれを理解し、受け入れるためには継続的なコミュニケーションが欠かせません。しかし、多くの企業では理念が一度発表されただけで終わり、その後のフォローアップが不足しています。社員は「企業理念」という言葉を聞くものの、それが自分の仕事にどう結びつくのかを深く考えることは少ないのです。コミュニケーションの不足は理念の浸透を妨げる大きな障害となります。
③ 経営層と社員の意識の差
経営層が企業理念を作成した背景には、企業全体の戦略やビジョンが反映されています。しかし、現場の社員はその理念を自分の業務や職務にどう結びつけるかがわからないことが多いです。特に、経営層と現場の社員の間に意識の差があると、理念が形骸化してしまうことがあります。経営層は理念の重要性を強調する一方で、現場ではその重要性を感じることができず、理念の実践が乏しくなってしまうのです。
④ 理念の具体化不足
企業理念が抽象的であっても、それを具体的な行動基準や方針に落とし込むことができれば、社員はその理念を日常業務に生かすことができます。しかし、多くの企業では理念がそのまま掲げられるだけで、具体的なアクションプランが示されていないケースが多いです。この場合、社員は理念に対して漠然とした理解しかできず、結果として理念が行動に移されることがありません。
⑤ 組織文化とのズレ
企業理念はその企業の文化を形成するための基盤となるべきものですが、もし企業の文化と理念にズレがある場合、社員は理念に共感しづらくなります。例えば、企業文化が「結果主義」を重視している場合、理念として「チームワーク」を重視するものが掲げられると、社員はその両者の違いに混乱し、理念の実践に消極的になる可能性があります。理念と文化の一致がなければ、理念は社員にとって現実的ではなく、結果として浸透しないことになります。
企業理念を実務に落とし込んだ成功事例
企業理念を浸透させるためには、経営層が積極的に社員と共に理念を具体的な行動に落とし込むことが不可欠です。以下に、企業理念を実務に落とし込んだ成功事例を紹介します。
成功事例❶ 山陽製紙株式会社(大阪府)
山陽製紙株式会社は、大阪府に本社を構える中堅の製紙メーカーで、環境に配慮した製品づくりを行っています。同社は、2007年に「紙づくりを通して環境に配慮した循環型社会に貢献する」という経営理念を制定しました。

理念浸透のため、社員が自発的に地域の川の清掃活動を行い、環境意識を高める取り組みを実施しました。また、社員全員が「eco検定」や「CSR検定」を受験し、環境や社会貢献に関する知識を深めています。さらに、毎年「理念祭」を開催し、社員が理念を体感し、共有する機会を設けています。
これらの取り組みにより、社員の環境意識が高まり、理念が日々の業務に浸透。社員同士の信頼関係も強化され、組織全体のエンゲージメント向上につながっています。
成功事例❷ ジャパンフリトレー株式会社(茨城県)
ジャパンフリトレー株式会社は、茨城県に本社を置くスナック菓子の製造・販売を行う企業で、「マイクポップコーン」や「ドリトス」などのブランドを展開しています。
同社は、2023年12月に中長期経営計画と企業理念を発表し、理念の浸透と体現に向けた活動を開始しました。具体的には、社員が理念を理解し、行動に移すための研修やワークショップを実施しています。また、理念を日常業務に落とし込むためのガイドラインや評価制度の整備も進めています。

理念の浸透と体現に向けた活動の結果、社員の意識改革が進み、現場でのコミュニケーションが活性化しました。また、採用活動においても企業理念を重視する姿勢が共感を呼び、優秀な人材の確保につながっています。
成功事例❸ オルバヘルスケアホールディングス株式会社(岡山県)
オルバヘルスケアホールディングス株式会社は、岡山県に本社を置く医療機器や介護用品の販売を行う企業で、2021年に創業100周年を迎えました。

同社は、企業理念を「社員憲章」として明文化し、「われわれは誰か」「誰のために、何をするのか」「どうありたいと願うのか」を明確にしています。また、創業者の価値観を「商道六か条」として継承し、社員全員にカードとして配布しています。さらに、理念浸透のための研修や社内イベントを定期的に開催しています。
社員憲章カードは、社員の理念理解が深めるだけでなく、業務における判断基準として活用されています。同時に、企業文化の醸成や社員のモチベーション向上にも好影響を及ぼしています。
社員が企業理念を理解し、業務に活かすようになるための3つの取り組み
社員が企業理念を理解し、それを日々の業務に反映させるためには、以下にある3つの取り組みが効果的です。いずれも、理念を「伝える」だけで終わらせず、「実感し、腹落ちさせる」段階にまで高めることを重視しています。
① 理念を“自分ごと化”できる仕組みをつくる
企業理念が社員にとって意味を持つためには、それが「自分の仕事とどうつながっているか」を理解できる必要があります。そのためには、理念と日常業務の接点を明示する工夫が必要です。
たとえば、職種や部署ごとに「この業務は、企業理念のどの要素を体現しているか?」を言語化する取り組みが有効です。実際に、理念と業務を紐づけた事例共有会や、社員が自ら理念に沿った取り組みを発表する機会を設けることで、「理念は現場から遠い存在」ではなく「自分の判断や行動の軸」であることを実感させることができます。
② 経営層の“言葉と態度”に一貫性を持たせる
社員が理念を本気で信じられるかどうかは、経営層の姿勢に大きく左右されます。口では理念を語っていても、経営判断や人事評価が理念と矛盾していれば、社員は理念を「建前」と捉え、真剣に向き合うことはありません。
成功している企業では、たとえば理念に基づいた意思決定をした事例を社内で明確に共有し、理念を体現した社員をきちんと評価・表彰する仕組みがあります。「理念を守ることで得をする」ことが、社員の行動原理として定着していくのです。
③ 理念を“体験”できる場を定期的につくる
理念はテキストとして読ませるだけでは腹落ちしません。理念を実感できる体験の場を通じてこそ、社員の意識に根付いていきます。
たとえば、理念をテーマにしたワークショップや合宿、または社外ボランティア活動など、日常とは違う文脈で「理念を考える」「行動する」場を設けることは、非常に効果的です。特に新入社員や中堅層の節目でのこうした機会は、理念の再認識と再定義につながります。
理念を言葉だけでなく“行動や感情”と結びつけることによって、理解が一層深まり、行動にもつながっていきます。
まとめ
社員が企業理念を理解していないのは、単に「説明が足りない」からではありません。多くの場合、理念が日々の業務や自分の役割と結びついていない、あるいは“自分ごと”として捉えられていないことが原因です。そしてそれは、理念そのものの表現のわかりにくさ、共有のタイミングの乏しさ、組織内のコミュニケーション構造など、複合的な要因が重なって生じています。
経営層と現場では見ている視点や時間軸が異なるからこそ、理念の共有は「伝えたつもり」で済まされがちです。しかし、理念が形骸化していれば、企業の進む方向は内側からぶれ始め、組織のまとまりや意思決定の一貫性にも影響を及ぼします。
理念の浸透は、現場の理解力や姿勢の問題ではなく、構造と設計の課題です。理念を伝えるという行為を、戦略的に再設計すること——すなわち、「どんな表現で」「誰が」「どのタイミングで」「どのように伝えるのか」を見直すことが、社員が企業理念を理解するための第一歩になります。
支えるブランド推進室
最新レポート
関連レポート
ブランドライブラリー
ブランドライブラリーの
最新情報

そのブランドに、
次の一手を。
「まだ依頼するか決めていない」段階でも、
多くの相談をいただいています。
-
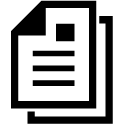
社内検討や実施
判断に活用できる
PDF資料を
ご用意しています -
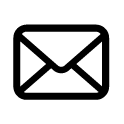
ご質問・ご相談は
フォームより
お問い合わせ
ください -
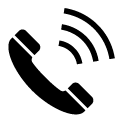
担当者が
直接ご対応します
10時〜18時
(平日)
このレポートについて
フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター
広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。
これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。