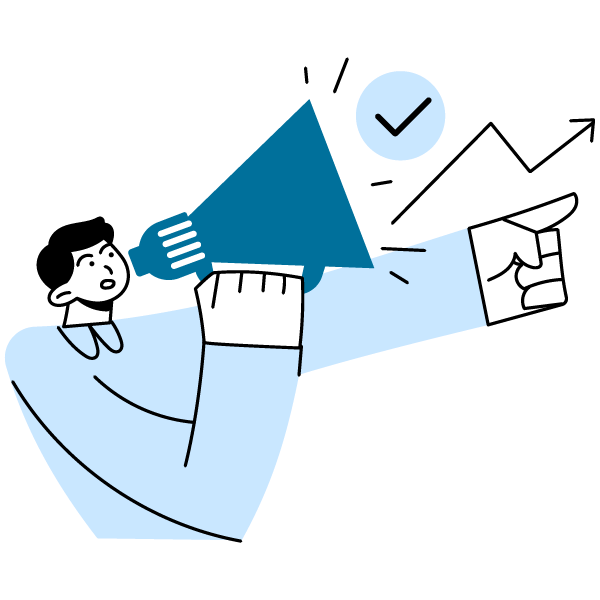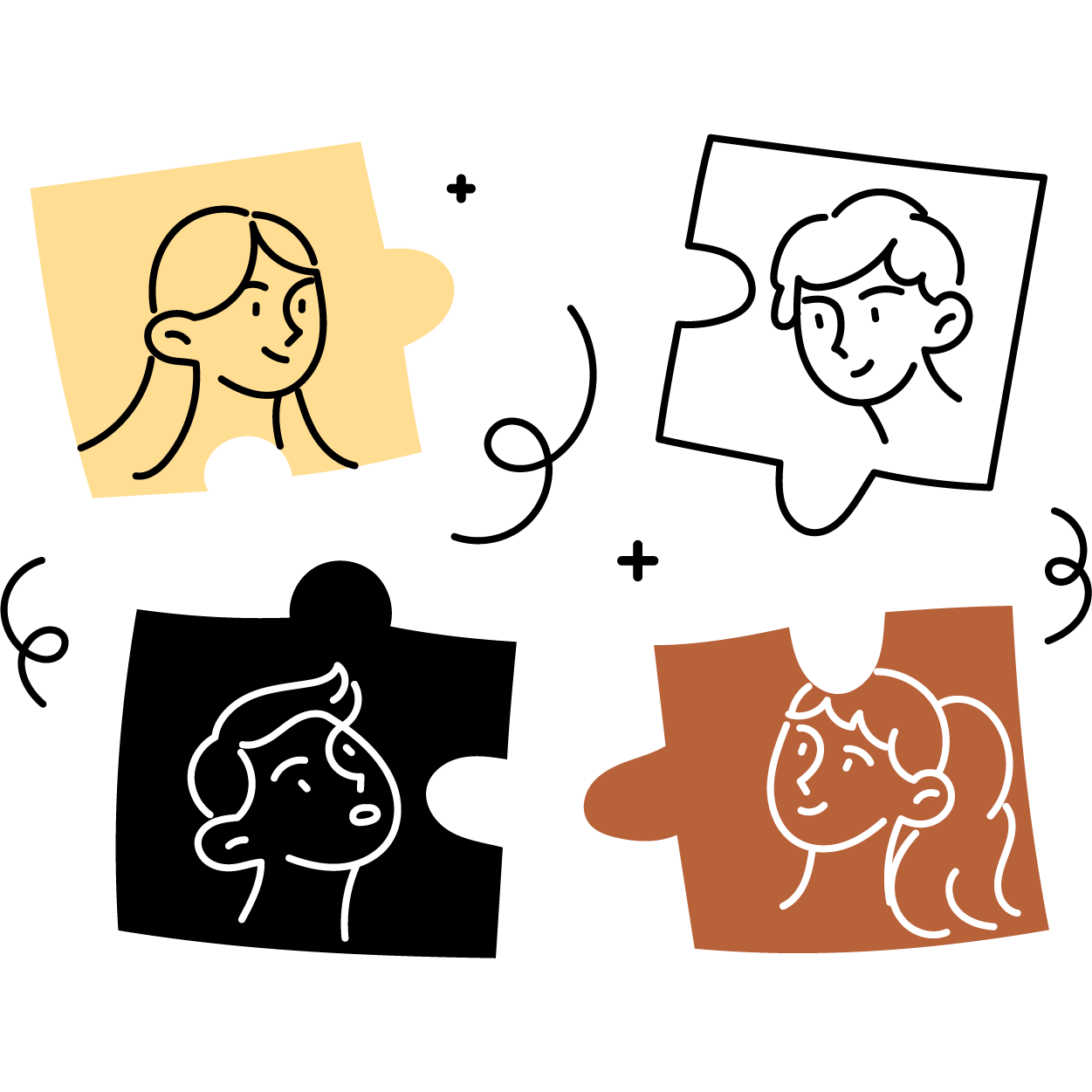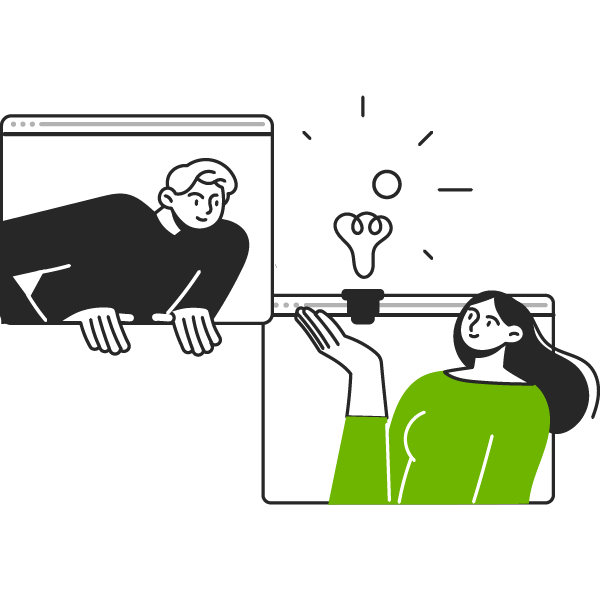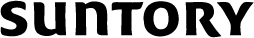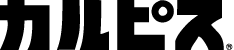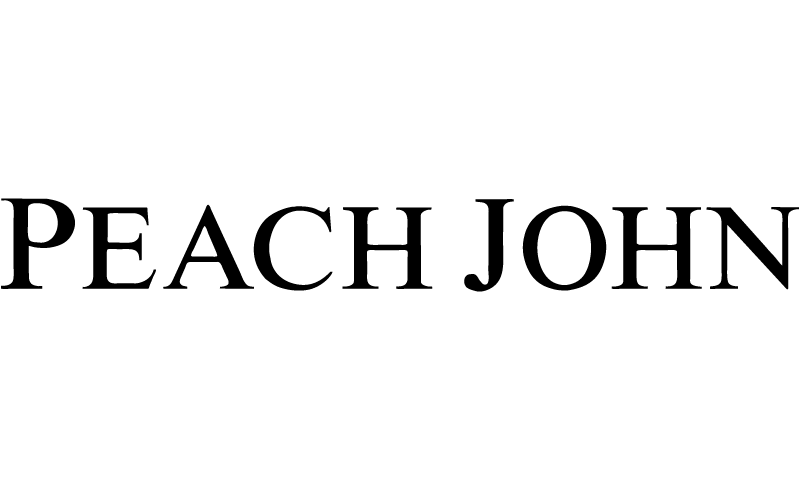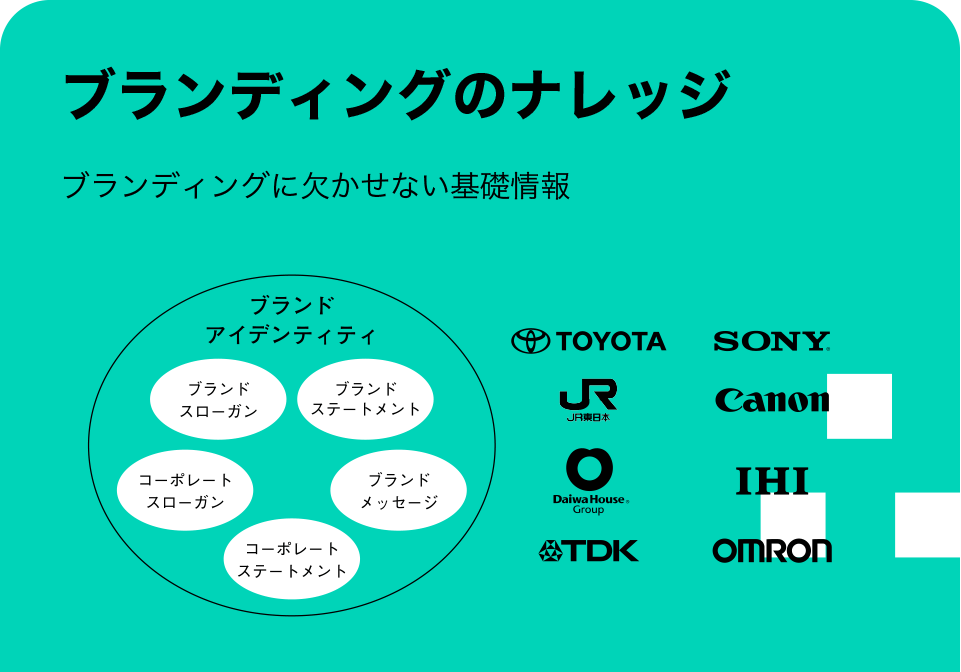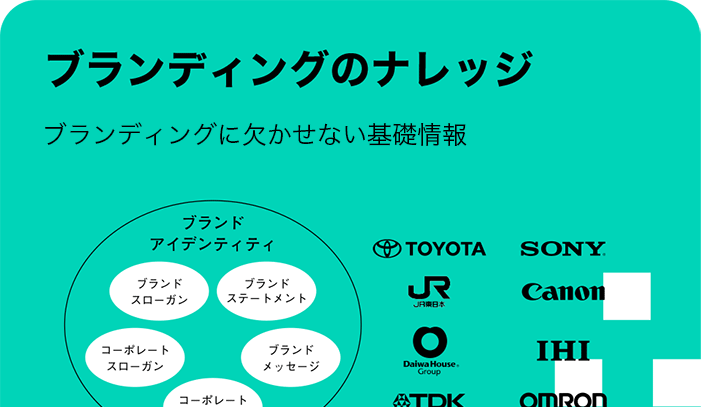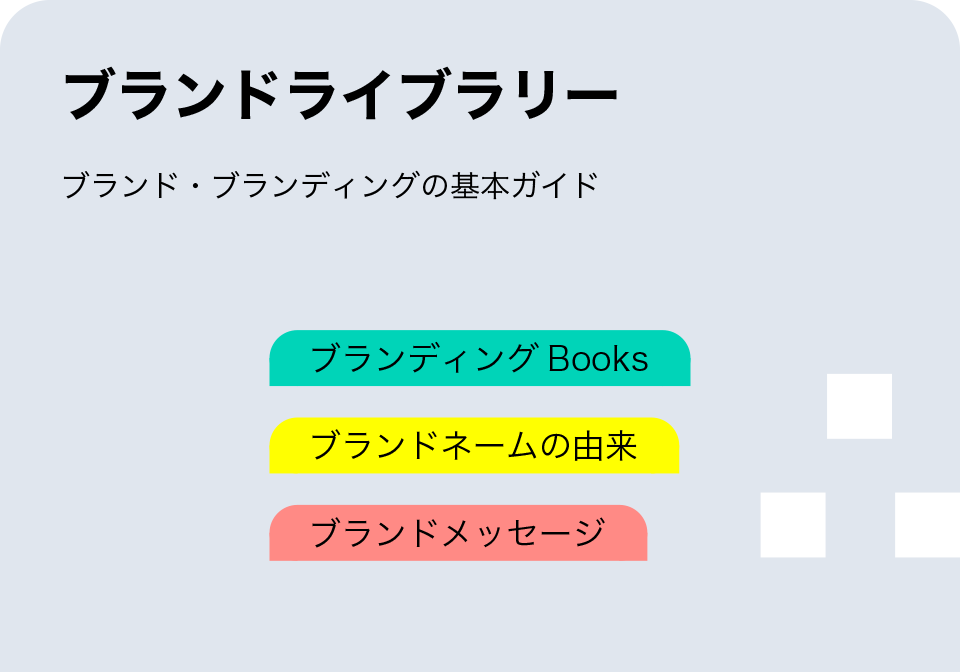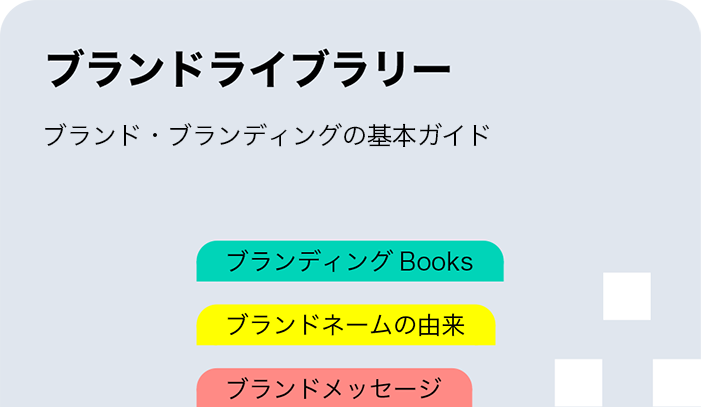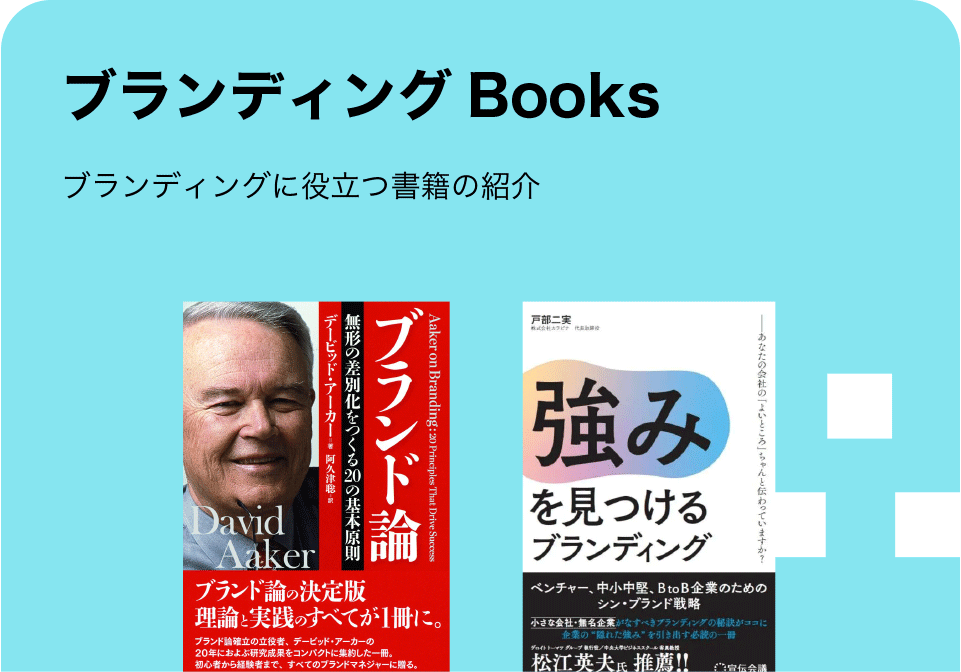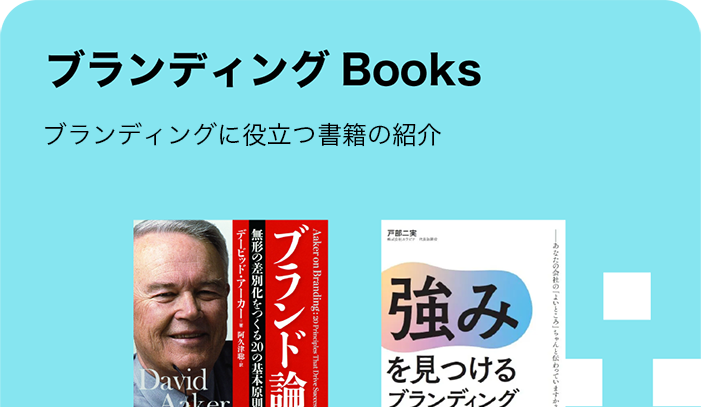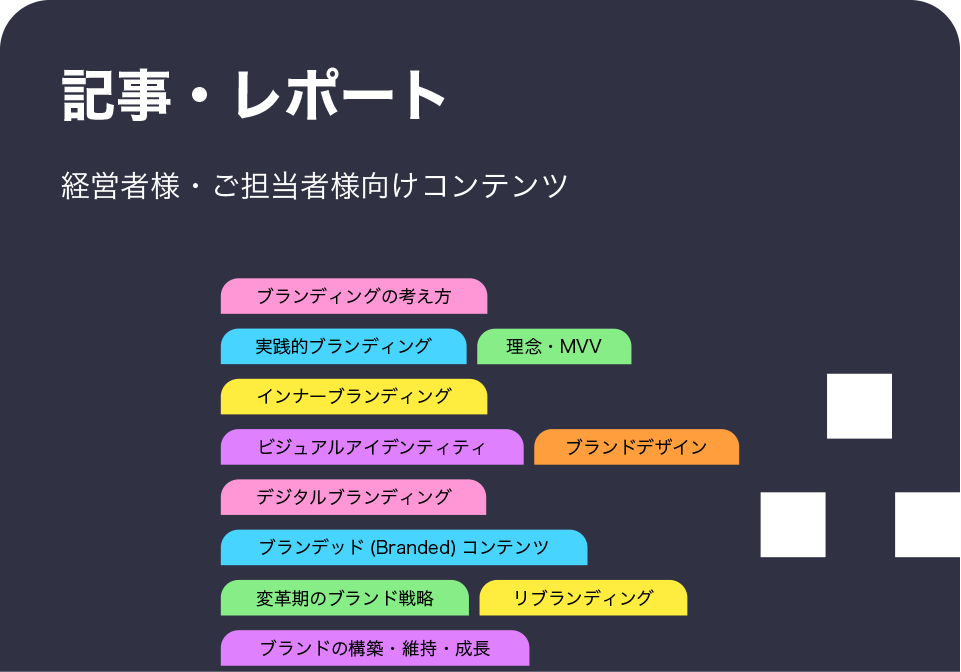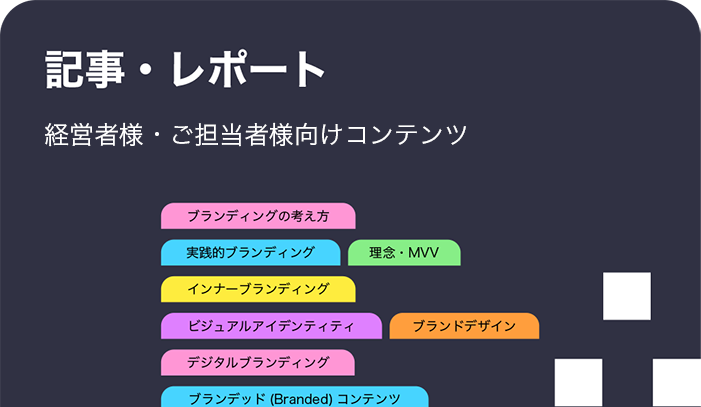インナーブランディング
企業ブランドを「社内から強くする」ための戦略と事例
2025年7月17日11分読み
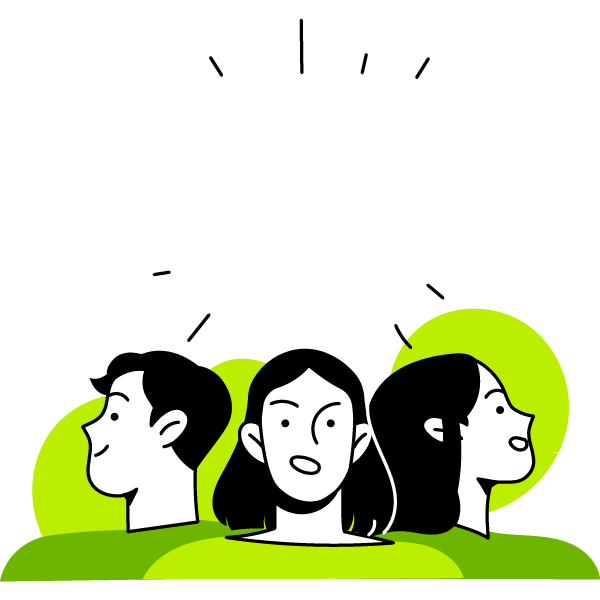
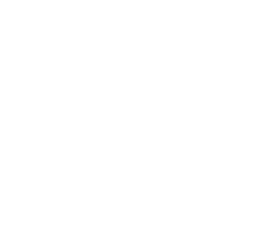
エグゼクティブサマリー
ブランディングは「社外」を意識した施策に目が行きがちですが、その本質的な価値は「社内」の在り方にも深く関係します。なぜなら社員がブランドの意義を理解し、自ら体現するようになって初めて、一貫した価値提供を行うことが可能になるからです。
本レポートでは、企業ブランドを「社内から強くする」ための戦略と、実際の企業の実践事例をもとに、その効果や取り組みのポイントをわかりやすく解説します。社員の共感や主体性をどのように育てていくかを掘り下げながら、ブランドが社内外で連動して機能する仕組みを探ります。
なぜ、企業ブランドを「社内から強くする」必要があるのか?
近年、企業ブランディングの重要性はますます高まっています。その効果は単に「外部への認知」や「市場における競争力」に留まらず、組織文化や社員の意識にも深く関わっています。実際、理念やブランドの価値観が社員の行動基準として根づくことで、顧客対応や業務判断に一貫性が生まれ、企業ブランドは外部からも信頼されるものへと強化されていきます。
ブランドは、社員一人ひとりの判断や行動を通じて具体的に形づくられていきます。どれだけ優れた理念やビジョンを掲げていても、それが現場の振る舞いや社内文化に反映されていなければ、外部に対して一貫した価値提供はできません。ブランドの強さとは、ブランドの“あるべき姿”を社員が無理なく体現できているかどうかに表れます。
さらに社員が自社ブランドに誇りを持ち、その一員としての意義を感じることは、企業にとって非常に重要な意味を持ちます。これにより社員のエンゲージメントが向上し、定着率が改善されるほか、採用競争力の強化にも繋がります。こうした内発的なブランド強化は、社員の定着率や働きがいにも直結します。特に人材不足が深刻化している現在、企業の魅力や価値観を明確に示すことは、採用力強化や離職率低下にもつながり、結果的に企業の成長基盤を支える重要施策となります。
社内からブランドを強くする実践事例
事例❶ 味の素株式会社(従業員数:約32,000名)
味の素株式会社は、「おいしく食べて健康づくり」という創業時からの志を守り続けながら、時代に即した価値創造のあり方を常に見直してきました。この姿勢は、企業ブランドを社内から強くするための戦略にも色濃く反映されています。
同社が導入したASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)は、企業活動を通じて社会価値と経済価値の両立を図る取り組みであり、経営と一体化した考え方です。ASVを軸としたマネジメントサイクルにより、社員一人ひとりが自らの業務を通じて社会課題の解決に関与できるようになっています。この仕組みにおいて重要なのは、「変えるもの」と「変えないもの」を明確にし、それを全社で共有している点です。
- 変えないもの:
創業から続く理念や、「おいしく食べて健康づくり」という志、生活者との信頼関係など、企業の根幹をなす価値観。これらはブランドの不変的な基盤として、すべての活動の出発点になっています。 - 変えるもの:
社会や市場のニーズ、テクノロジーの進化に応じて、商品開発や働き方、事業の焦点を柔軟に変革。ASVサイクルを活用して、新しい時代の課題に対応する価値創出の方法を常に進化させています。
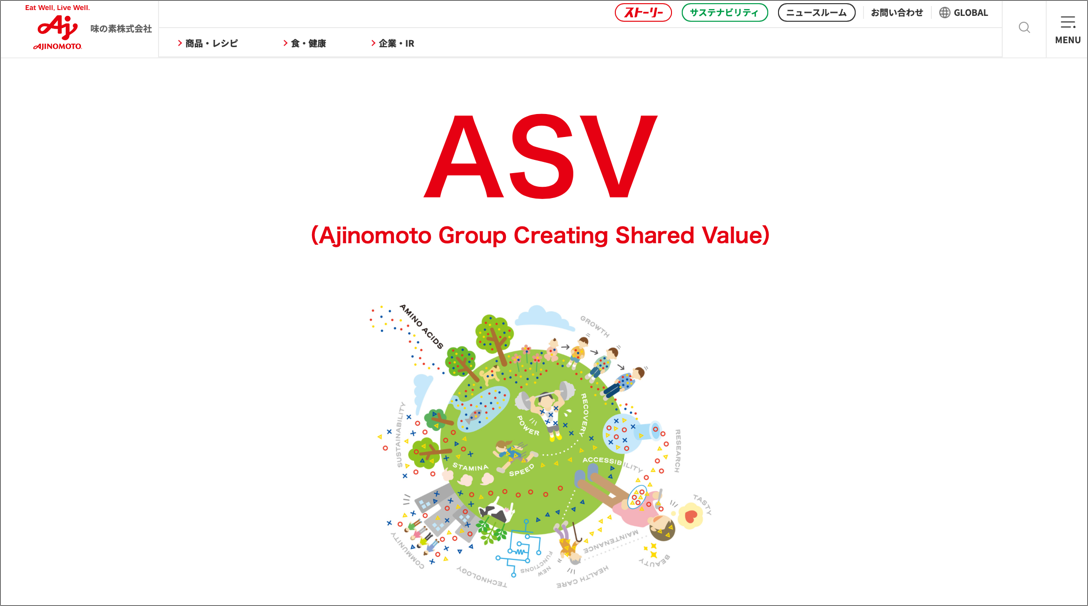
さらに優れた実践を称える「ASVアワード」を社内で開催し、ブランド理念の具体的な表現とその成果を全社で共有。理念が日常の業務にどう結びつくかを「見える化」することで、社員の主体性と一体感が高まっています。
事例❷ コマツ(小松製作所)(従業員数:約63,000名)
コマツ(小松製作所)は、企業理念「コマツウェイ」の浸透を通じて、社内からブランドを強化する取り組みを積極的に進めています。この「コマツウェイ」は、マネジメント/リーダーシップ、ものづくり、ブランドマネジメントの3つの軸から構成され、全社員が共有すべき価値観と行動規範を明文化したものです。

具体的な施策として、コマツはデジタルトランスフォーメーション(DX)人材の育成に注力しています。2019年度からAI人材教育を開始し、2022年度からはDX人材教育を導入しました。これらの教育プログラムは、基礎知識の習得を目的とした入門教育から、業務課題の解決を目指す実践教育まで、段階的なカリキュラムで構成されています。2023年度末までに、5,643名が入門編、84名が実践編を受講し、社員のリスキリングとスキルアップに貢献しています。
また、コマツはダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進にも力を入れています。2023年度には、国内グループ全社員を対象にD&Iに関するeラーニングを展開し、管理職向けには心理的安全性に関するセミナーを開催しました。さらに、女性社員のキャリア意欲を高めるため、経営層と直接対話できる「D&Iトークイベント」を実施し、社員から高い満足度を得ています。これらの取り組みにより、コマツは社内からブランドを強化し、持続可能な企業価値の向上を実現しています。
企業ブランドを社内から強くするための3つの取り組み
企業ブランドを社内から強くする取り組みには、社外発信と同様もしくはそれ以上に、社内での戦略設計と実行が欠かせません。その主要な取り組みを、以下に3つ紹介します。
① 経営層からの一貫した発信と姿勢の徹底
企業ブランドを社内に根付かせるには、経営層が旗振り役となり、自らの言葉と行動でブランドの方向性を示すことが欠かせません。理念や価値観を宣言するだけに留めず、社内会議・社内報告・社内制度設計などあらゆる場面で一貫して語ることで、社員の信頼と共感を得ることができます。
たとえば、経営メッセージにブランドの価値観を明示し、幹部層の評価制度にもその実践を組み込むなど、トップから現場へと理念を貫く仕組みが重要です。単なる「言葉」ではなく、「判断の拠り所」として社内の意思決定に反映されていくと、ブランドが自然と企業の文化となっていきます。
② 社員一人ひとりが主体的に関われる仕組みづくり
ブランドを「自分には関係ない」と感じる社員が多い組織では、どれほど立派な理念であっても形骸化してしまいます。社員がブランドの考え方を自らの業務に引き寄せ、自分の言葉で語れるようにすることが、ブランドを社内から強くするための核心だと言えます。
たとえば、「自社らしい仕事とは何か」を社員自身が定義するワークショップや、日々の行動とブランド価値との接点を確認できる研修プログラムなどを通じて、自社ブランドの解像度を上げることは効果的です。こうした場があることで、社員は企業ブランドの担い手としての意識を持つようになり、日常的な判断や行動にもその軸が現れていきます。
③ 社員による「実践」の成果を見える化し、共有する
ブランドの価値を実感できるようにするには、社員による「実践」の成果を社内で見える形にすることが不可欠です。ここでの「実践」とは、理念や価値観に沿った行動・判断・提案などを指します。
たとえば、理念に基づいた顧客対応や業務改善を社内表彰する制度、ブランドに即したプロジェクトをイントラネットで紹介する取り組みなどがあります。こうした「見える化」により、ブランドが組織全体で共有され、社内における成功事例として連鎖していきます。成果を認識し、称賛する文化は、ブランドの定着だけでなく、エンゲージメントやモチベーションの向上にもつながります。
まとめ ―企業ブランドを「社内から強くする」ために―
企業ブランドを「社内から強くする」ための戦略は、単なるマーケティング戦略以上に、企業そのものの競争力を底上げする力を持っています。ブランド理念が社員に浸透し、日々の業務に反映されることで、組織は自然とブランドらしい意思決定や行動をとるようになります。
その結果、社内の一体感が生まれ、社員のモチベーションやエンゲージメントが向上し、ひいては定着率や採用力の強化といった人的資本への好影響も期待できます。ブランドは「社外に向けた顔」であると同時に、「社内を動かす力」でもあるのです。
企業ブランドの強化を考える上で、まず内側に目を向けること。これが、持続的なブランド価値の創出に不可欠な第一歩です。
支えるブランド推進室
最新レポート
関連レポート
ブランドライブラリー
ブランドライブラリーの
最新情報

そのブランドに、
次の一手を。
相談からはじめる、成果が見える
ブランディング
-
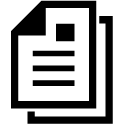
サービス内容・
特徴・実績を
まと
めたPDF資料を
ご活用ください -
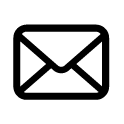
ご質問・ご相談は
フォームより
お問い合わせ
ください -
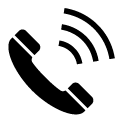
担当者が
直接ご対応します
10時〜18時
(平日)
このレポートについて
フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター
広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。
これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。