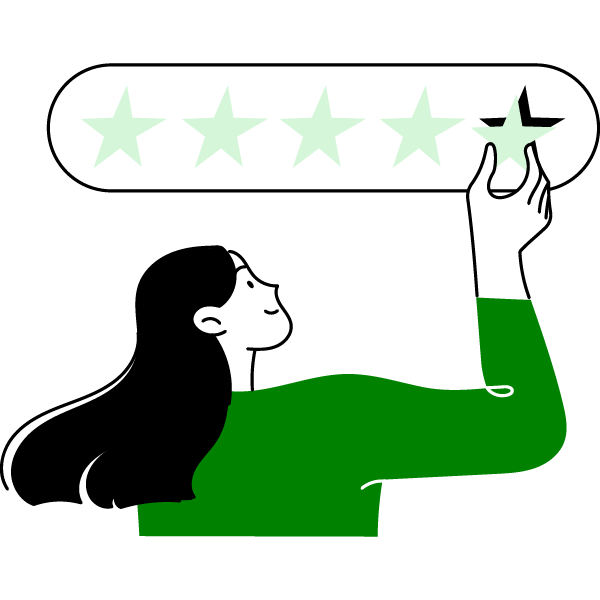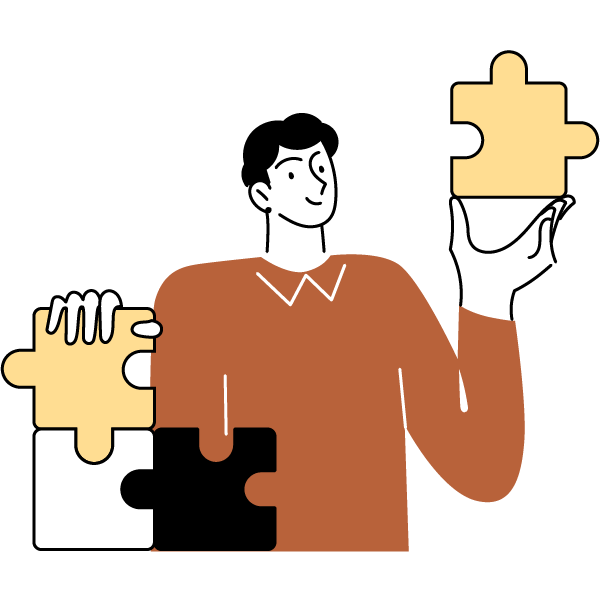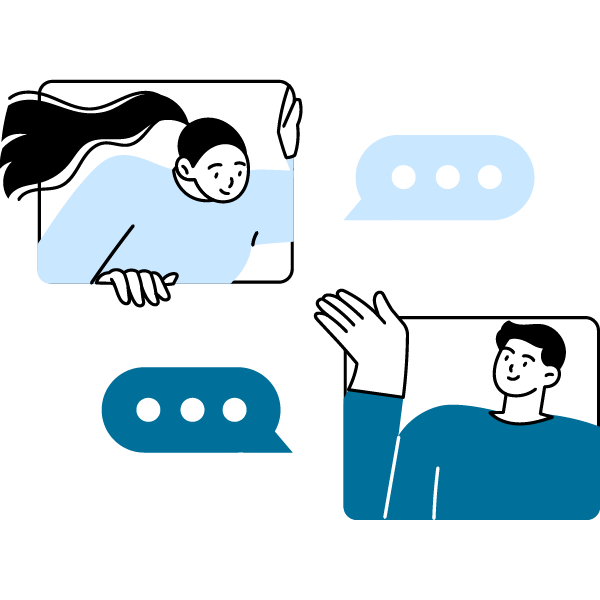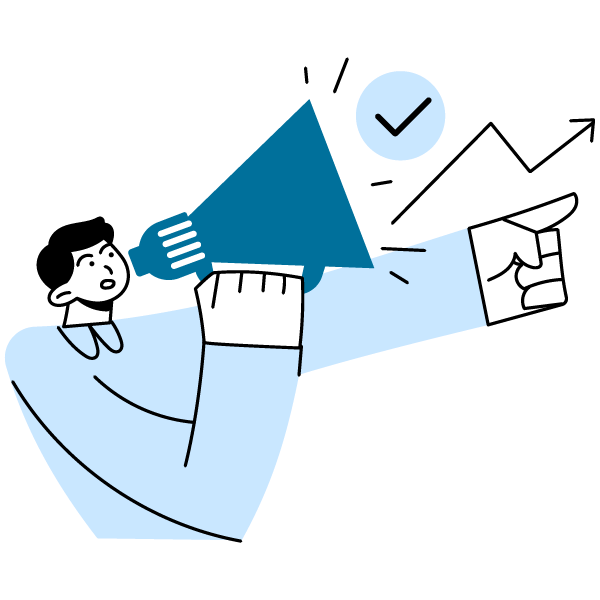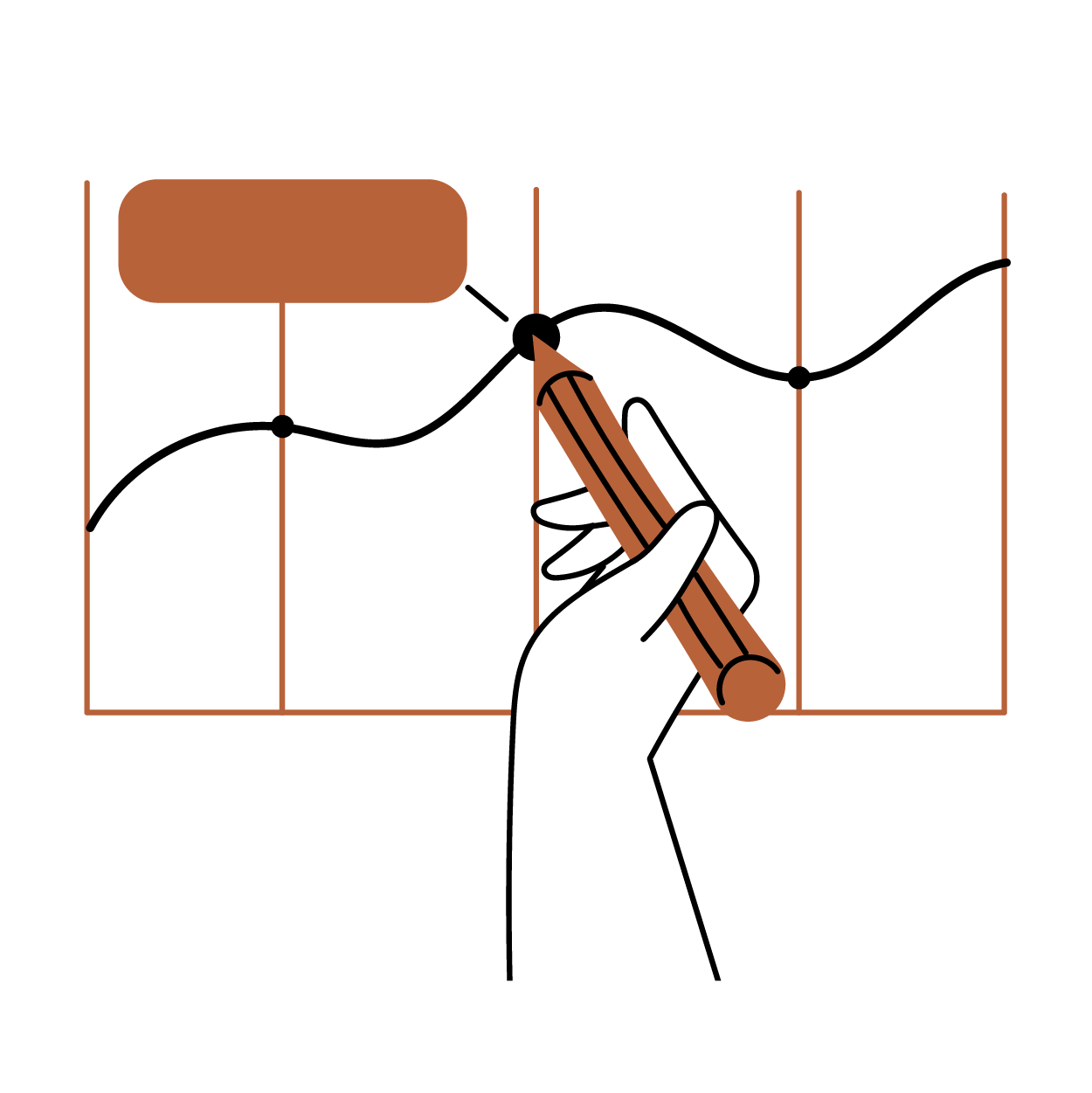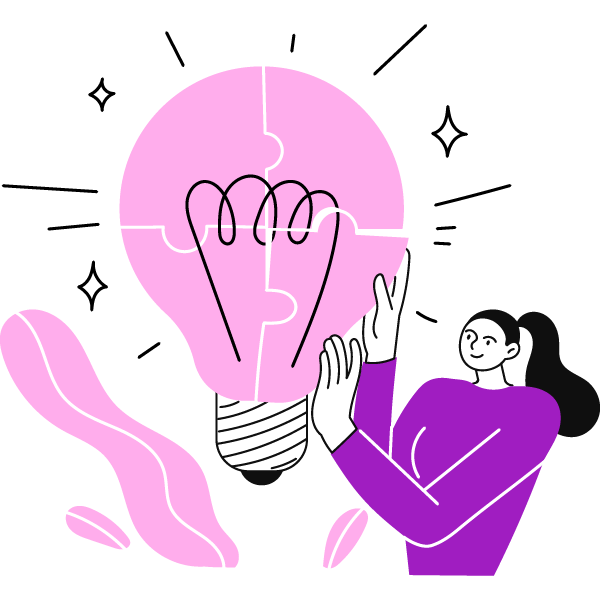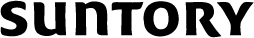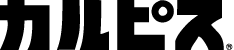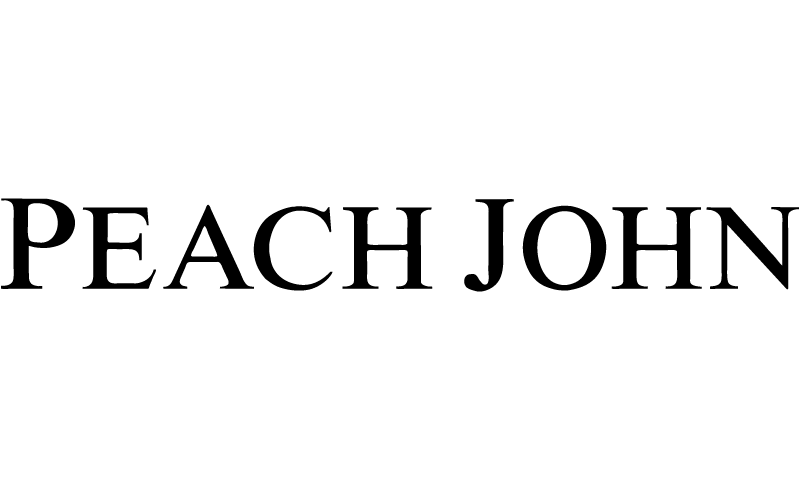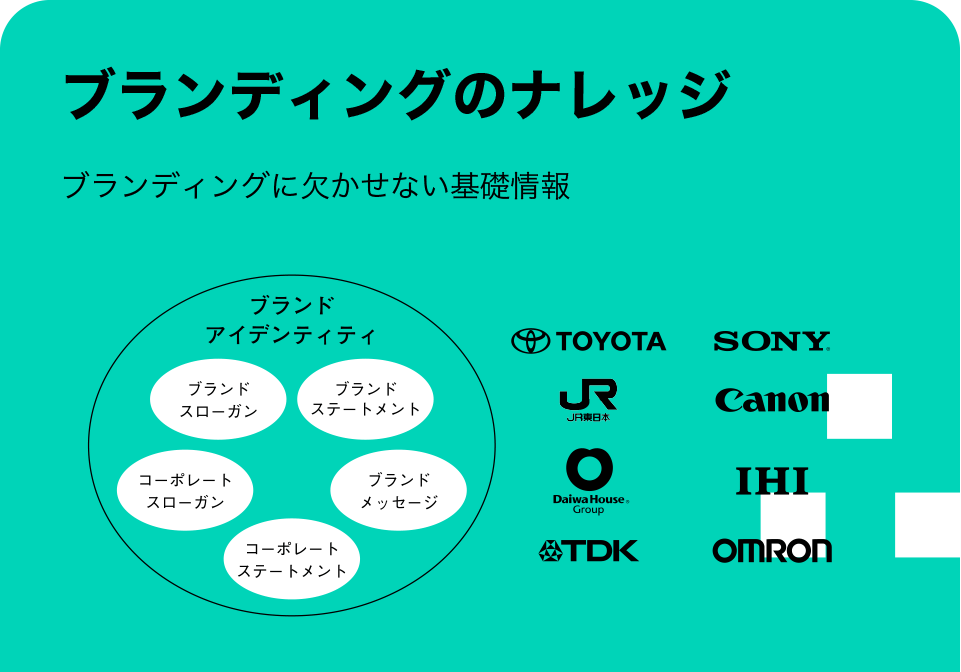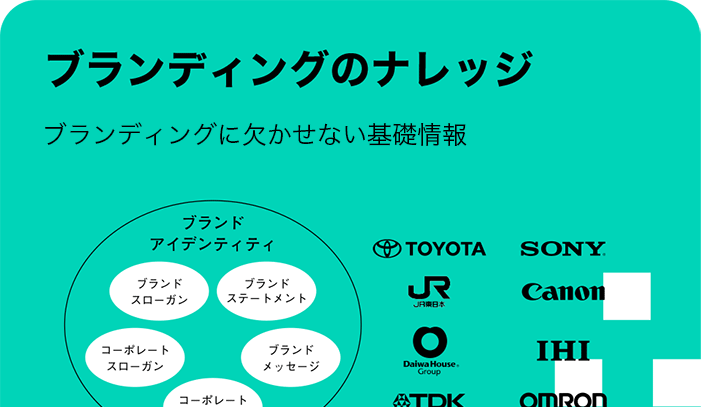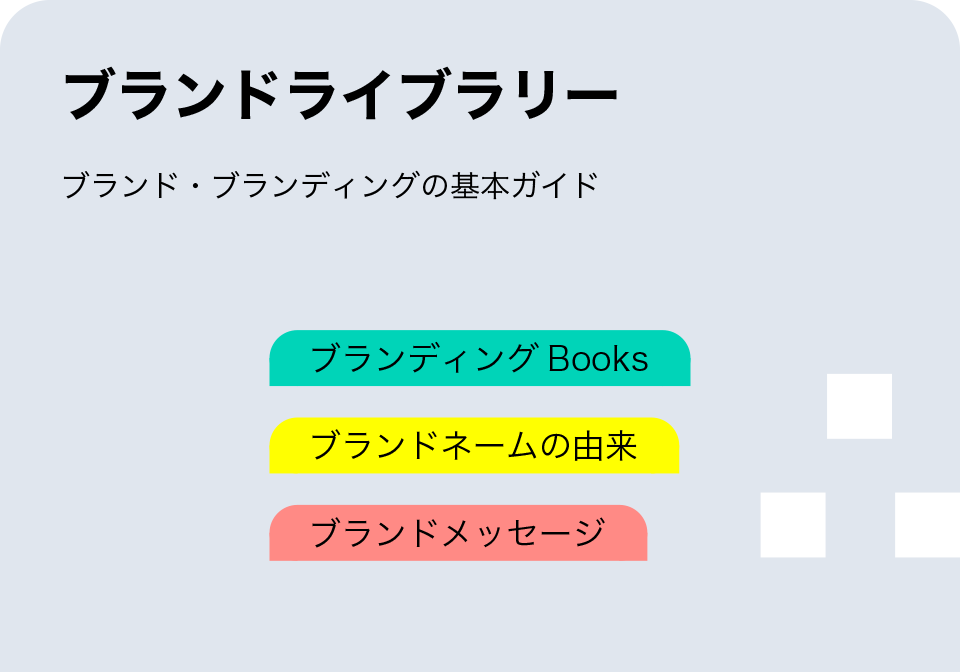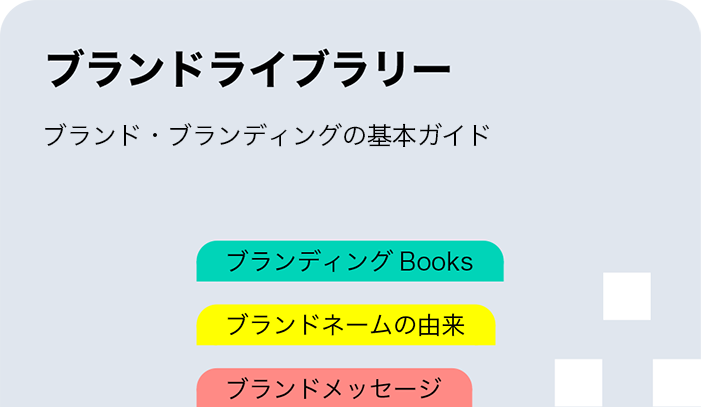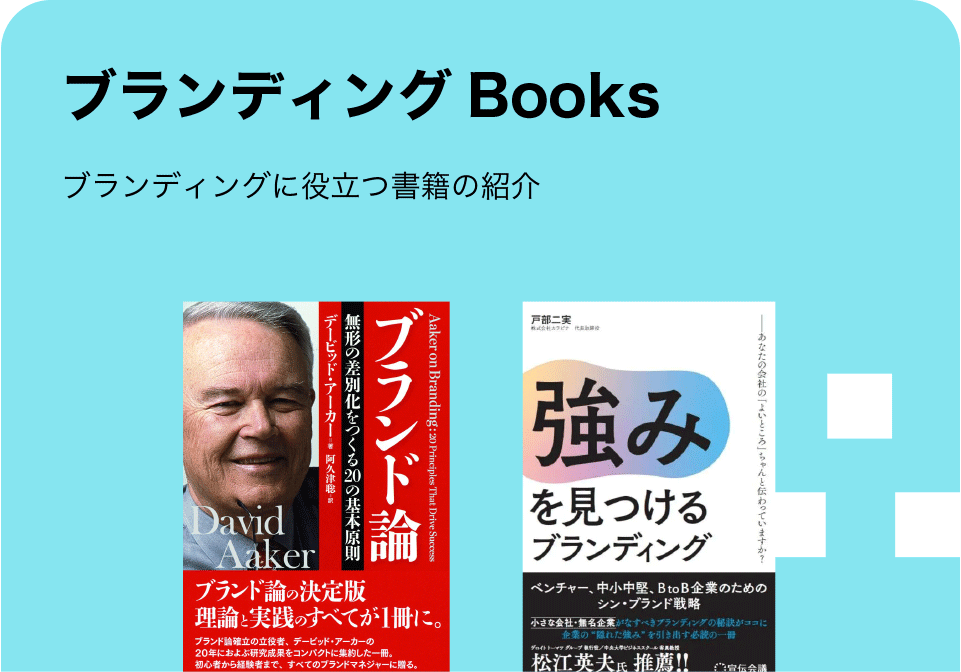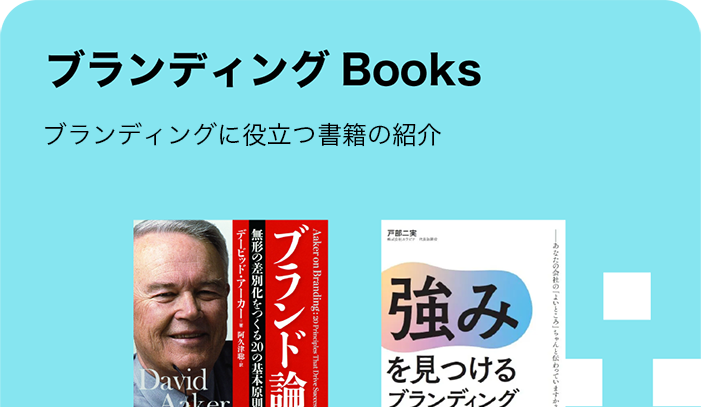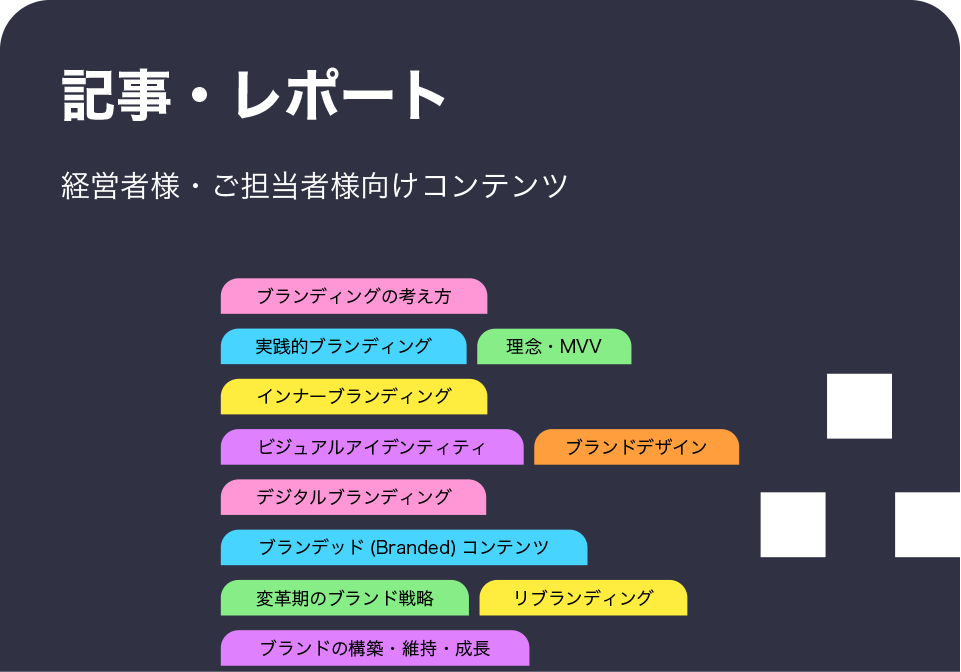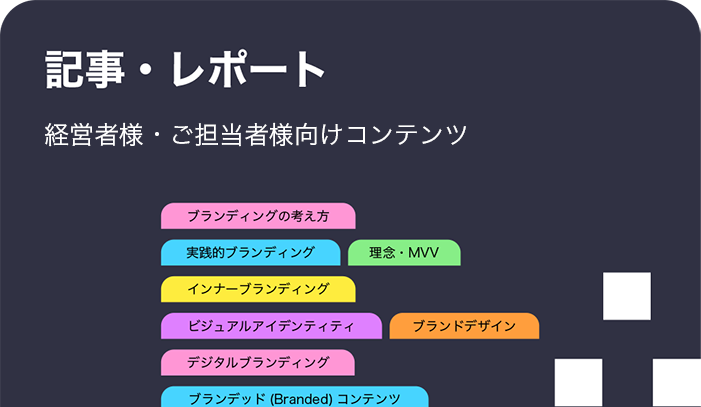ブランデッド(Branded)コンテンツ
共感が連鎖するブランデッドコンテンツ ──“知ってもらう”から、“感じてもらう”へ
2025年3月24日 9分読み

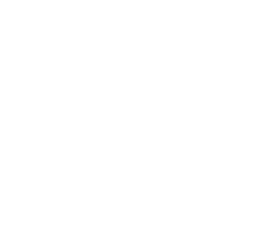
エグゼクティブサマリー
近年、企業と生活者の関係性は大きく変化しています。単なる商品の魅力や価格だけで選ばれる時代から、「共感」や「意味」によって支持される時代へと移行しています。そのなかで注目を集めているのが「ブランデッドコンテンツ」です。これは、企業が自社の価値や世界観を物語るコンテンツを通じて生活者と深い関係を築く手法であり、近年では大企業に限らず、中堅・中小企業においても導入の動きが広がっています。
本レポートでは、ブランディングの専門的な視点をもとに、ブランデッドコンテンツの本質とその進化について解説します。加えて、日本の中小企業が実際にどのようにこの手法を活用し、成果をあげているのかを事例として紹介しながら、成功のポイントや実践上の留意点についても整理していきます。経営者やブランド担当者にとって、今後のブランド投資の方向性を見極めるヒントになれば幸いです。
ブランデッドコンテンツとは何か
ブランデッドコンテンツとは、企業の提供する価値や世界観を、広告的要素ではなく「コンテンツ」として発信する手法です。たとえば、動画や記事、イベント、マンガなど、形式は多岐にわたりますが、いずれにも共通しているのは「商品の直接的な訴求を控えつつ、企業の哲学や世界観を伝える」という点にあります。
近年では、SNSやYouTubeなどのプラットフォームを活用することで、従来のマスメディアに頼らずとも、特定のターゲットに向けた発信が可能となりました。中堅・中小企業にとっても、適切な企画と制作体制があれば、限られた予算内で強いブランドメッセージを伝えることができる時代が到来しているのです。
ブランデッドコンテンツは、従来の広告と異なり、短期的なレスポンスではなく、中長期的なブランド好感度や信頼の醸成を目的としています。これは、製品を売る前に「共感」を売る、いわば“関係性づくり”のブランディングであるといえるでしょう。
ブランデッドコンテンツの展開事例
事例❶ 「地元工務店のYouTube戦略」―にいはら工務店
千葉県大網白里市に本社を構える「にいはら工務店」は、注文住宅やリフォームを手がける地域密着型の工務店です。自社ブランド住宅「S-CRAFT」の魅力を伝える手段として、同社は早くからYouTubeでの発信に注力してきました。営業色を抑え、住まいへの考え方や施工事例を紹介する動画は、結果として自社の世界観や価値観を伝えるブランデッドコンテンツとなり、共感を集めています。
同社が運営する「S-CRAFT公式チャンネル」では、平屋コンパクトハウスの間取りや施工事例、イベント情報などを定期的に配信。これにより、広告費を抑えながらも見込み客との接点を築き、注文住宅の受注につなげる仕組みを構築しました。そして登録者数が1万人を超えると反響が加速し、月平均20件以上の問い合わせ、40組以上の来場を獲得します。こうしてモデルハウスを持たずとも受注を継続できる体制を確立できたことで、住宅フランチャイズ「S-CRAFT」を全国に展開。現在では9社の加盟店を抱えるまでに成長しています。

このケースは、ブランデッドコンテンツを起点とする発信が、ブランドの認知と信頼、そして新たな事業機会へと結実した好例と言えるでしょう。
事例❷ 「共感と信頼の醸成に重きを置いたコンテンツ」―サイボウズ株式会社
サイボウズ株式会社が運営する「サイボウズ式」は、企業が自らの思想や価値観を社会に伝えるブランデッドコンテンツの好例です。自社製品の宣伝を目的とせず、「働き方」や「チームワーク」をテーマに、企業の価値観を伝える場として機能しています。

「100人いれば100通りの働き方があっていい」という思想のもと、制度や文化の背景にある考え方を丁寧に言語化。数値的なKPIを追わず、共感と信頼の醸成に重きを置いたコンテンツは、月間20〜40万PVを安定的に集め、他メディアにも数多く取り上げられるなど、広報効果を生んでいます。また、「サイボウズ式を読んで応募した」という採用応募者の声が社内でも共有されるなど、採用ブランディングにも実際に貢献しており、ブランドへの共感や企業理解を促す手法として有効に機能しています。
成功させるための要素と陥りやすい落とし穴
ブランデッドコンテンツを成功させるためには、いくつかの重要な要素があります。第一に、自社ならではの「語るべき価値」を明確にすることです。どの企業にも、創業の想いや顧客への姿勢、地域や社会との関係など、固有の物語が存在します。これを言語化し、コンテンツの中心に据えることが不可欠です。
次に重要なのは「継続性」です。ブランデッドコンテンツは、一度の発信で劇的な成果を出すものではありません。むしろ、時間をかけて信頼や共感を積み重ねていくものです。したがって、単発の施策で終わらせず、定期的にコンテンツを届ける姿勢が求められます。
一方で、陥りやすい失敗も存在します。代表的なのが、「過度な演出」や「広告臭の強さ」です。ユーザーは本質的な“物語”を求めており、表面的な装飾や強引な商品訴求に敏感です。また、社内の共感が得られていないまま進めると、発信内容と現場の実態が乖離し、かえって信頼を損なう結果にもなりかねません。
ブランデッドコンテンツの実践に向けたロードマップ
では、ブランデッドコンテンツに取り組むにあたって、最初に着手すべきことは何でしょう。第一歩は「ブランドの棚卸し」です。自社の強み、歴史、こだわり、社風、地域との関係性など、これまで当たり前と思っていたものを改めて見つめ直すことが出発点になります。
そのうえで、「誰にどんな印象を届けたいか」という視点で、発信テーマを設計します。発信媒体は、必ずしもYouTubeやウェブサイトに限りません。例えば、地域イベントへの出展や小冊子の配布など、オフラインの手法も有効です。重要なのは、自社らしいスタイルで無理なく続けられる仕組みをつくることです。
また、外部の専門家や制作パートナーと協働することで、コンテンツの質を担保しつつ、社内の負担を軽減することも可能です。小さく始めて、試行錯誤しながら育てていく柔軟さが、成功の鍵に他なりません。
まとめ ―ブランデッドコンテンツの展望―
ブランデッドコンテンツは、単なる情報発信の手法ではなく、企業の姿勢や価値観を社会と共有するための“文化的な営み”ともいえます。大企業だけでなく中堅・中小企業にとっても、“価格や機能の競争”ではない“意味の競争”が進むなかで、こうした取り組みはますます重要性を増しています。
本レポートで紹介したように、特別な制作技術や大規模な予算がなくても、自社らしい視点と継続的な姿勢があれば、ブランドは確実に深化していきます。ブランデッドコンテンツは、企業と顧客のあいだに信頼を育て、やがては“選ばれる理由”となっていくでしょう。
これからの時代、ブランディングとは「声の大きさ」ではなく「語る中身とその信頼性」で決まっていきます。ぜひ、自社の原点を見つめ直し、物語る力を磨いていくことから始めてみてください。
支えるブランド推進室
最新レポート
関連レポート
ブランドライブラリー
ブランドライブラリーの
最新情報

そのブランドに、
次の一手を。
「まだ依頼するか決めていない」段階でも、
多くの相談をいただいています。
-
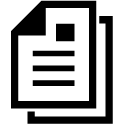
社内検討や実施
判断に活用できる
PDF資料を
ご用意しています -
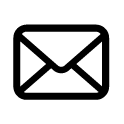
ご質問・ご相談は
フォームより
お問い合わせ
ください -
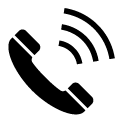
担当者が
直接ご対応します
10時〜18時
(平日)
このレポートについて
フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター
広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。
これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。